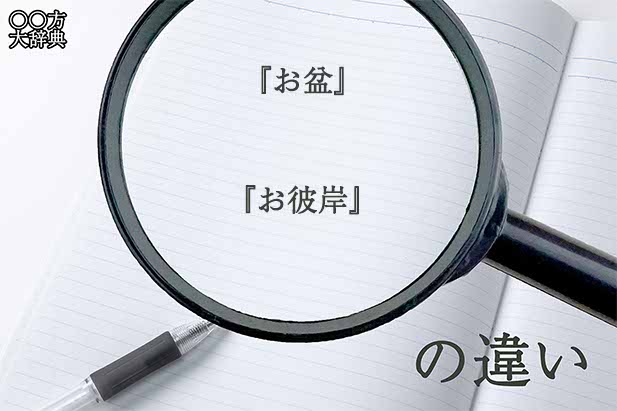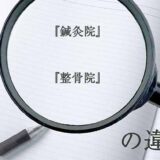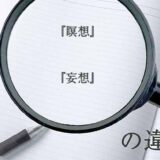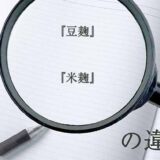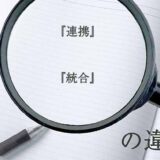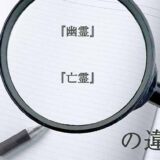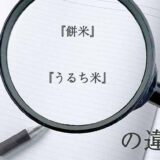この記事では『お盆』と『お彼岸』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『お盆』の意味とは
お盆は、日本の伝統的な行事であり、先祖の霊を迎えて供養する時期を指します。お盆は基本的には8月13日から15日までの3日間ですが、地域によっては7月13日から15日までの3日間のこともあります。この期間中、先祖の霊が生前の家に帰ってくるとされ、家族でお墓参りをし、供え物をすることが一般的です。また、盆踊りや提灯の飾り付けなど、地域によってはさまざまな風習や行事が行われます。
類語・言い換えや詳細
1. 供養
2. 先祖の霊
3. お墓参り
4. 提灯の飾り付け
5. 盆踊り
『お彼岸』の意味とは
お彼岸は、仏教の行事であり、春分と秋分の日を中心に行われます。お彼岸は一般的に、春分の日前後の数日間(春彼岸)と秋分の日前後の数日間(秋彼岸)を指します。お彼岸では、先祖の霊を供養し、家族の絆を深めるために、お墓参りを行います。また、お盆と同様に供え物をし、心を清めることも大切な行事です。
類語・言い換えや詳細
1. 仏教の行事
2. 春分と秋分の日
3. 春彼岸と秋彼岸
4. お墓参り
5. 供え物
6. 心を清める
『お盆』と『お彼岸』の違いと使い方
お盆とお彼岸は、いずれも先祖の霊を供養するための行事ですが、異なる意味や使い方があります。お盆は、特に先祖の霊が生前の家に帰ってくるとされ、家族でお墓参りや供物をすることが重視されます。一方、お彼岸は春分と秋分の日を中心に行われ、先祖の霊を供養し、絆を深めるためにお墓参りを行います。また、お墓参りの他に心を清めるための儀式が行われることもあります。
例えば、お盆の時期には、地域ごとに盆踊りや提灯の飾り付けが行われることがありますが、お彼岸にはこれらの行事はありません。また、お盆では先祖の霊が帰ってくるとされるため、帰省して家族揃ってお墓参りをすることが一般的ですが、お彼岸では日中にお墓参りをすることが一般的です。
まとめ
お盆とお彼岸は、似ているようで異なる意味や使い方があります。お盆は家族で先祖の霊を迎えるための行事で、お墓参りや供物が重視されます。一方、お彼岸は春分と秋分の日にお墓参りをし、心を清めるための行事です。どちらも先祖への感謝の気持ちや絆を大切にする意味が込められており、日本の文化として大切にされています。