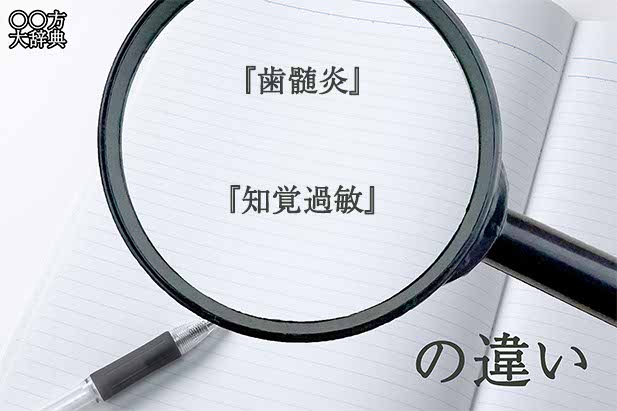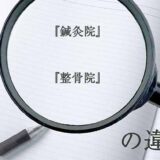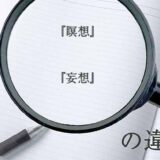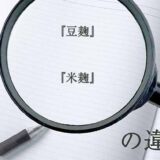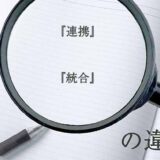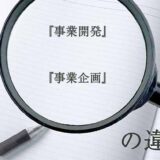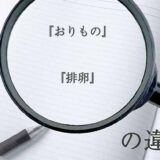この記事では『歯髄炎』と『知覚過敏』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『歯髄炎』の意味とは
歯髄炎は、歯の内部にある歯髄(歯の神経組織)が炎症を起こす病気です。主な原因は虫歯や歯の根の感染です。症状は強い歯の痛みや腫れ、過敏などが現れます。
類語・言い換えや詳細
1. 虫歯の進行によって発症することが多い
2. 歯の根の感染も原因の一つ
3. 症状は歯の痛み、腫れ、過敏など
『知覚過敏』の意味とは
知覚過敏は、歯のエナメル質や歯根の表面が削れてしまったり、歯茎が退縮してしまうことによって起こる症状です。冷たい飲み物や温かい食べ物を口にすると、鈍い痛みやしみる感覚があらわれます。
類語・言い換えや詳細
1. エナメル質の削れや歯茎の退縮によって起こる
2. 冷たい飲み物や温かい食べ物で痛みやしみる感覚が現れる
3. 歯のエナメル質や歯根の表面の傷が原因
『歯髄炎』と『知覚過敏』の違いと使い方
歯髄炎と知覚過敏の違いは、発生する原因と症状にあります。歯髄炎は主に虫歯や歯の根の感染が原因で起こり、強い歯の痛みや腫れを引き起こします。一方、知覚過敏は歯の表面の傷や歯茎の退縮によって起こり、冷たい飲み物や温かい食べ物で痛みやしみる感覚が現れます。使い方では、歯髄炎は歯の内部の炎症を指すため、歯髄炎が起こるときに使用します。一方、知覚過敏は感覚が過敏になることを指すので、知覚過敏がある場合に使用します。
まとめ
『歯髄炎』と『知覚過敏』は、歯の問題を表す言葉であり、異なる症状や原因を持っています。歯髄炎は歯の内部に起こる炎症で、虫歯や歯の根の感染が主な原因です。知覚過敏は歯の表面の傷や歯茎の退縮によって起こり、冷たい飲み物や温かい食べ物で痛みやしみる感覚が現れます。正しい使い方を知り、適切な対策を行いましょう。