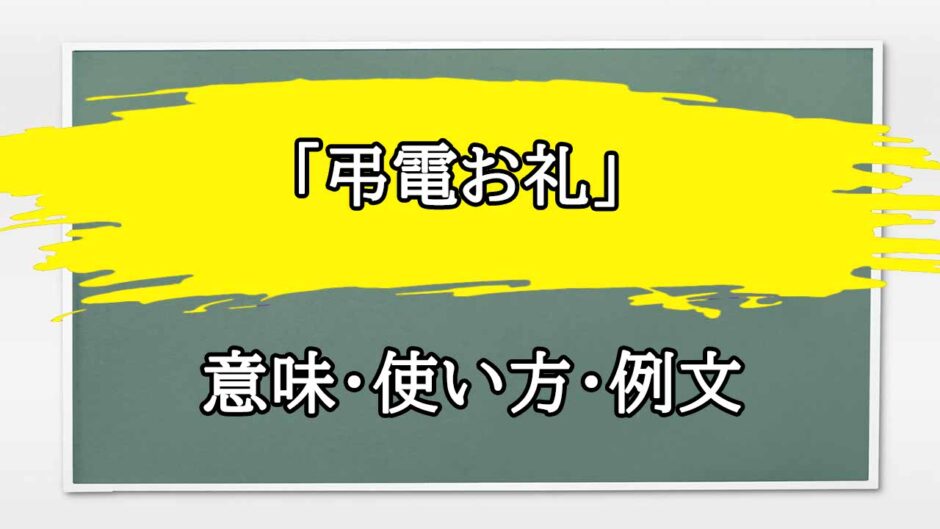弔電お礼とは、喪中や葬儀に参列した際に送られるお礼の電報のことを指します。
この慣習的な行動は、亡くなった方やその家族への敬意や感謝の気持ちを表すものです。
弔電お礼は、喪主または葬儀委員会などが代表的な送信者となり、喪家の連名で送られることが一般的です。
このような形でお礼を伝えることで、参列者の気持ちに寄り添うと同時に、亡くなった方のご冥福を祈るという思いも込められています。
では、詳しく紹介させて頂きます。
「弔電お礼」の意味と使い方
意味:
「弔電お礼」とは、故人を偲び、その家族や関係者に謝意を表すために送られる電報のことを指します。
故人の葬儀や通夜などに参列した人々が、葬儀後に家族に向けて感謝の意を伝える手段として利用されます。
弔電お礼は、喪主や親族からの感謝の気持ちを伝えるための共通の形式となっており、社会的な儀礼として重要視されています。
使い方:
弔電お礼は、故人の葬儀や通夜などの後、喪主や親族が送ることが一般的です。
以下は、弔電お礼の例文です。
例文1:故人のためにお世話になりました。
このたびは誠にありがとうございました。
ご多忙の中、弔問にお越しくださり、また弔電お礼までいただき、心より感謝申し上げます。
例文2:葬儀のお手伝いにお越しくださり、誠にありがとうございました。
亡き〇〇の想い出を皆様と一緒に追悼できたこと、心より感謝いたしております。
弔電お礼もお送りさせていただきましたので、どうぞご覧ください。
弔電お礼の書き方や内容は、地域や習慣により異なる場合がありますので、参考にする際は周囲の相談者や文化に合わせて適切な表現を行うことが重要です。
弔電お礼の間違った使い方の例文とNG部分の解説
NG例文1:
「ご愁傷さまです。
ありがとうございました。
」
NG部分の解説:
弔電のお礼では、相手の方にお悔やみの気持ちを伝える必要があります。
「ご愁傷さまです」という表現は、喪主や近親者に向けた言葉ですが、お礼のメッセージでは適切ではありません。
相手方に対して、「ご愁傷さまです」という言葉を返すことで、気持ちを受け止めていることを伝えるべきです。
NG例文2:
「合災祭ありがとうございました。
」
NG部分の解説:
「合災祭」という表現は、台湾や中国の特定の地域で行われる祭りの名称ですが、日本の弔電のお礼には使用されません。
正しくは「弔電ありがとうございました」という表現を使うべきです。
また、お礼のメッセージでは、相手方が送ってくれた弔電への感謝の気持ちを表現するため、「ありがとうございました」という言葉を追加することが重要です。
NG例文3:
「悲報に接しました。
心よりお礼申し上げます。
」
NG部分の解説:
お礼のメッセージでは、「悲報に接しました」という表現は避けるべきです。
相手方には弔電を送ることで、喪失や悲しみに直面していることが伝わっていますので、改めて悲報を言及する必要はありません。
お礼のメッセージは、相手方に対して感謝の気持ちを伝えることに焦点を当てるべきです。
例文1:
弔電ありがとうございますお目通しのお言葉に心から感謝いたします。
亡くなった方のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様には慰めと支えがありますように願っております。
書き方のポイント解説:
弔電を受け取った場合、感謝の気持ちを伝えることが重要です。
直接的でシンプルな表現を使い、相手に対する感謝の気持ちを明確にしましょう。
また、亡くなった方やご遺族に対しても思いやりを示し、お祈りの言葉を添えることが望ましいです。
例文2:
お弔電をいただき、ありがとうございますご心配とお見舞いのお言葉に感謝いたします。
ご遺族の皆様の悲しみを少しでも軽くできるよう、心からお祈りいたします。
書き方のポイント解説:
お弔電を受け取った場合、相手のご心配とお見舞いの言葉に感謝することを伝える必要があります。
また、ご遺族の悲しみを和らげることを願ってお祈りの言葉を述べましょう。
思いやりと共感を示す表現を使うことで、相手に寄り添ったメッセージを伝えることができます。
例文3:
心温まるお弔電をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです亡きXXさんに対するおことばと暖かいお支えに深く感謝申し上げます。
ご遺族の皆様の側にいらっしゃる時、お力になれるように努めて参ります。
書き方のポイント解説:
心温まるお弔電に対して感謝の気持ちを明確に伝えることが重要です。
亡くなった方に対する思いやりと共に、ご遺族の皆様へのサポートを示す言葉を添えましょう。
自身の努力を表現することで、相手への支援意思を示すことができます。
例文4:
突然の訃報に接し、お気持ちをお察し申し上げますご家族の皆様には深い哀悼の意をお伝えいたします。
亡くなった方も、きっとXXさんの思い出を大切にし、見守ってくださっていることでしょう。
書き方のポイント解説:
訃報を受けた場合、相手のお気持ちを察する言葉を使うことが大切です。
ご家族の皆様への哀悼の意を表し、亡くなった方の存在を敬意を持って確認しましょう。
思いやりを込めた言葉遣いで、相手の悲しみに寄り添ったメッセージを伝えられます。
例文5:
お悔やみのお電話をいただき、心から感謝しております亡くなられたXXさんのご冥福を心からお祈り申し上げます。
どうかご遺族の皆様が、平穏な時間を過ごせるよう心からお祈りいたします。
書き方のポイント解説:
お悔やみのお電話を受け取った場合、感謝の気持ちを表現することが大切です。
亡くなった方に対して敬意を示し、ご遺族の皆様の安らぎを願うお祈りの言葉を込めましょう。
思いやりと共感を伝える表現を使うことで、相手に寄り添ったメッセージを伝えられます。
弔電お礼の例文についてまとめると、弔電を送ったり受け取ったりする際、適切なお礼の言葉を伝えることが大切です。
例文を通じて、きちんと感謝の気持ちを伝えることができるようにしましょう。
お礼の文は簡潔でありながらも心からの感謝の気持ちを表現することが重要です。
例文は以下のようなパターンがあります。
1. 弔電を受け取った場合:「お悔やみのお言葉をいただき、心より感謝申し上げます。
大切な方の訃報に接し、皆様からのお気遣いに深く感謝しております。
心強いお言葉に励まされ、家族一同、立ち直る力をいただいております。
このようなご時世では、直接お礼をお伝えすることが難しい状況ですが、心の中でお礼を申し上げるとともに、感謝の気持ちを大切にし、故人のご冥福をお祈りすることでお礼とさせていただきたいと思います」2. 弔電を送った場合:「この度は大切な方の訃報を受けまして、心からお悔やみ申し上げます。
どうしても直接お会いすることが難しいですが、お寂しいお気持ちを思いながら、弔電をさせていただきました。
少しでもお力になれるような言葉を選び、お伝えできるように努めました。
どうか、ご家族の悲しみが少しでも癒えることをお祈りしております。
改めて、心よりご冥福をお祈り申し上げます」以上のように、弔電お礼の例文では、お悔やみのお言葉をいただいたり、弔電を送ったりする際の感謝の気持ちを伝えることが大切です。
大切な方の思い出を共有し、共に感謝し合いながら、心の交流を深めることができるでしょう。