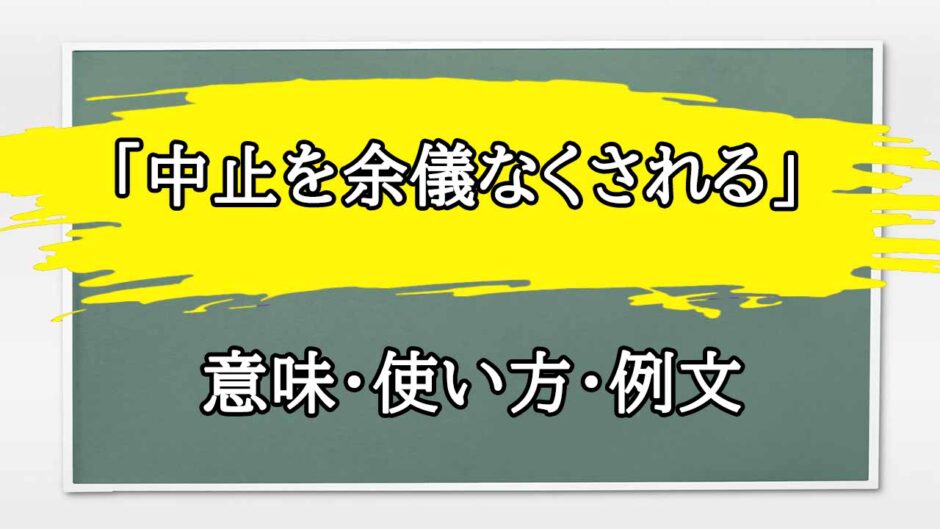「想定外の出来事や状況が発生して、計画や行動を中止せざるを得なくなることを、「中止を余儀なくされる」と言います。
この表現は、予期せぬ変化や動作の中断を強調する際に用いられることがあります。
仕事やイベント、旅行など、人々の日常生活においてもよく使われる表現です。
この表現の意味や使い方について、以下で詳しく紹介させていただきます。
それでは詳しく紹介させて頂きます。
」
「中止を余儀なくされる」の意味と使い方
意味
「中止を余儀なくされる」は、予定や計画が予期せぬ事情により中止されることを表す表現です。
何かの理由で続行が不可能な状況になり、計画やイベントなどが中止されることを示します。
使い方
例文:1. 彼らの結婚式は、新型コロナウイルスの拡大により中止を余儀なくされた。
2. 集会の開催場所が使用不可能になったため、イベントは中止を余儀なくされた。
3. 天候予報が荒天を予想したため、ピクニックは中止を余儀なくされた。
4. 重大な安全上の理由から、試合は中止を余儀なくされた。
この表現は、何か予期せぬ障害が発生したために、予定された活動やイベントが中断されることを説明する際に使われます。
中止を余儀なくされるの間違った使い方の例文とNG部分の解説
NG例文1:
旅行の計画を中止しなければならなかったので、とてもがっかりしました。
NG部分の解説:
「中止を余儀なくされる」という表現は、予期せぬ事情により計画を中止せざるを得なかった場合や、強制的に中止された場合に使われる表現です。
ただし、この例文では「中止しなければならなかった」という自分が決めた意志による中止を表現しているため、正しい使い方とは言えません。
NG例文2:
彼の態度にムカついたので今後の取引を中止することにしました。
NG部分の解説:
「中止することにしました」という表現は、自分の意志によって中止を決めた場合に使われます。
しかし、この例文では相手の態度によって中止を決めたため、自分の意志ではないために「中止することに決めた」という表現が適しています。
NG例文3:
試合が雨で中止になったので、楽しみにしていた友人との約束をキャンセルした。
NG部分の解説:
「中止になった」という表現は、予定されていたイベントや行事が天候などの理由により中止された場合に使われます。
しかし、この例文では試合が中止になったことが理由で友人との約束をキャンセルしたため、正しくは「キャンセルした」という表現が適しています。
中止を余儀なくされるの5つの例文と書き方のポイント解説
例文1:
天候の悪化により、ピクニックは中止を余儀なくされた。
書き方のポイント解説:
この例文では、明確な主語と動詞を使用しています。
また、「中止を余儀なくされる」という表現を用いることで、ピクニックが予定通りに行われなかった理由を強調しています。
例文2:
急な体調不良が発生し、試験は中止を余儀なくされた。
書き方のポイント解説:
この例文では、原因と結果を明確に示すことで、試験中止の理由を明確に伝えています。
また、「急な体調不良」「中止を余儀なくされた」という表現を使うことで、状況の緊急性を強調しています。
例文3:
予算の不足により、プロジェクトは中止を余儀なくされました。
書き方のポイント解説:
この例文では、明確な理由である「予算の不足」という要素を提示することで、プロジェクト中止の決断を正当化しています。
また、「中止を余儀なくされた」という言葉を使うことで、断念の決断が避けられない状況であったことを伝えています。
例文4:
極端な気候条件のため、イベントは中止を余儀なくされました。
書き方のポイント解説:
この例文では、気候条件が極端であったことを示す語句「極端な気候条件」という表現を用いています。
また、「中止を余儀なくされました」という言葉を使うことで、イベントの中止が避けられない事態であったことを強調しています。
例文5:
安全上の理由から、フライトは中止を余儀なくされました。
書き方のポイント解説:
この例文では、安全性の問題を強調するために「安全上の理由」という言葉を用いています。
また、「中止を余儀なくされました」という表現を使うことで、フライトが避けられない状況であったことを示しています。
中止を余儀なくされるの例文について:まとめ
中止を余儀なくされるという状況は様々な場面で起こることがあります。
例えば、予定されていたイベントや会議が突然中止になることもあります。
中止を余儀なくされる場合、関係者や参加者にとっては大きな影響を与えることがあります。
計画や準備をしていた時間や労力が無駄になるだけでなく、予定を変更しなければならないため、混乱や不便さも生じることがあります。
中止を余儀なくされる事例の中には、天候や自然災害によるものもあります。
たとえば、野外イベントやスポーツ大会は天候の変化によって中止が決定されることがあります。
これは安全面や運営の円滑さを考慮しての判断ですが、参加者や関係者にとっては非常に残念なことです。
また、予算や資金の都合によっても中止が必要となることがあります。
たとえば、企業のプロジェクトやイベントは予算の制約や資金不足によって中断されることがあります。
これは財務状況や経営戦略などを考慮した結果であり、無理な予算をかけることなく事業を進めるための決断と言えるでしょう。
中止を余儀なくされる場合は、関係者や参加者に事前に通知することが重要です。
円滑なコミュニケーションを行い、不都合や損失を最小限に抑えることが求められます。
また、中止の理由や代替案なども十分に説明することで、関係者の理解と協力を得ることができるでしょう。
中止を余儀なくされた場合でも、適切な対応や柔軟な考え方が求められます。
予期せぬ事態に対して冷静に対応し、新たな計画や対策を考えることで、より良い結果を得ることができるかもしれません。
中止を余儀なくされることは避けられない場合もありますが、適切な対応と十分な準備を行うことで、影響を最小限に抑えることができるでしょう。