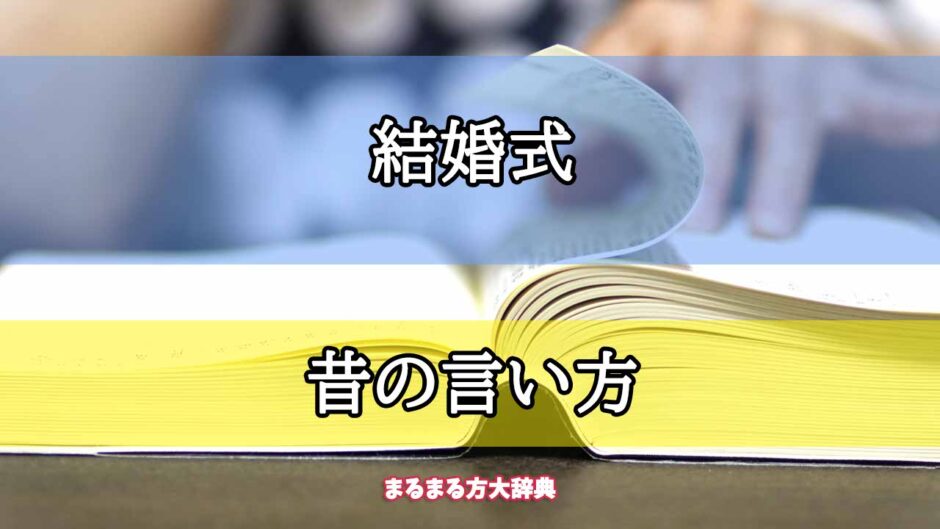「結婚式」の昔の言い方とは?結婚式を行う際に使われる表現は、時代と共にさまざまな変化を経てきました。
昔の言い方を知ることで、結婚式の歴史や文化に興味を持つことができるでしょう。
昔の結婚式を表現する言葉としては、「婚礼」という言葉があります。
この言葉は、古くから日本の結婚式の形式や儀式を指す言葉として使われてきました。
また、「結髪」という言葉も、昔の結婚式において新婦が髪を結う儀式を指す言葉として用いられていました。
結婚式を「婚礼」と呼び、「結髪」という儀式が行われる。
昔の結婚式を思い浮かべるだけで、神秘的で華やかな雰囲気が広がりますね。
それでは詳しく紹介させて頂きます。
昔の言い方とは
昔の言い方は、現在の言葉とは異なる古風な表現や敬語を使用して、過去の時代における文化や風習を表現する方法です。
結婚式においても、昔の言い方は特に重要であり、その時代の社会的な背景や風習を理解する上で役立ちます。
以下では、昔の言い方の例文とその解説をご紹介します。
おめでとうございます
昔の言い方:ご結婚おめでとうございます。
現代の言い方:結婚おめでとうございます。
昔の言い方では、「ご結婚」の敬称が使用されています。
敬称を使うことで、お祝いの意味をより強調することができます。
「おめでとうございます」は、現代でも使用される言い方ですが、昔の言い方ではより丁寧な表現となっています。
新郎新婦の挨拶
昔の言い方:末永くお幸せに。
現代の言い方:末永くお幸せに。
昔の言い方では、結婚式の最後に行われる新郎新婦の挨拶で使用されるフレーズです。
「末永くお幸せに」とは、長く幸せでありますようにという祝福の言葉であり、昔の言い方でも現代でも変わらず使用されています。
祝いの言葉
昔の言い方:百年のお幸せをお祈り申し上げます。
現代の言い方:幸せな結婚生活を送ってください。
昔の言い方では、「百年のお幸せをお祈り申し上げます」というより長い期間にわたる祝福の言葉が使用されています。
現代の言い方では、シンプルで直接的な表現が一般的ですが、昔の言い方ではより堅苦しい言葉遣いがされていました。
これにより、結婚式の場での祝福の気持ちがより深まったのです。
お色直し
昔の言い方:違う衣装にお着替えするのでございます。
現代の言い方:お色直しします。
昔の言い方では、お着替えすることを丁寧に表現しています。
「違う衣装にお着替えするのでございます」とは、お色直しの時間に行われる新婦の衣装の変更を指しています。
現代の言い方では、お色直しという言葉そのものが一般的になりましたが、昔の言い方ではより詳細な表現を用いることが一般的でした。
結婚披露宴
昔の言い方:お披露目を行うのでございます。
現代の言い方:結婚披露宴を行います。
昔の言い方では、「お披露目を行うのでございます」という表現が使用されています。
お披露目とは、結婚式のパーティーのことを指し、新郎新婦が公に結婚を発表する場です。
現代の言い方では、直接的かつシンプルな表現が一般的ですが、昔の言い方ではより礼儀正しい言葉遣いがされていました。
以上が「結婚式」の昔の言い方の例文と解説です。
昔の言い方を理解することで、結婚式の文化や風習をより深く知ることができます。
結婚式の昔の言い方の注意点と例文
注意点1: 敬語を用いる
結婚式は特別な儀式ですので、昔の言い方では特に敬意を表す敬語を使うことが重要ですね。
例えば、新郎新婦に対しては「御婚礼(ごこんれい)」と呼び、ご家族には「お儀式(おぎしき)」とおっしゃると、より正式さが表現されます。
注意点2: 謙譲語を使う
昔の言い方では、結婚式に関わる方々にも謙譲語を用いることが一般的でした。
たとえば、新郎新婦の両親には「御進物(ごしんもつ)」「御祝儀(ごしゅうぎ)」とおっしゃると、相手方に対する謙譲の心が伝わります。
注意点3: 感謝の気持ちを表現する
昔の言い方では、結婚式に参加する方々への感謝の気持ちを積極的に表現していました。
例えば、招待状や挨拶の際に「ご多忙中(ごたぼうちゅう)」「お目にかかる幸(さいわい)」「心からお礼を申し上げます」といった言葉を使うと、お世話になる方々に対する謙虚さと感謝の気持ちを示すことができます。
注意点4: 丁寧な表現を心掛ける
結婚式の昔の言い方では、特に丁寧な表現を心掛けることが重要でした。
例えば、ご両親や来賓に対しては、「住上り(すうじょうり)」「御足労(ごそくろう)」とおっしゃると、相手への敬意と丁寧さが感じられます。
例文1: 招待状の例文
拝啓、このたび、私たちの御婚礼(ごこんれい)が執り行われることとなり、大変喜んでおります。
御多忙中(ごたぼうちゅう)をおかけいたしますが、ぜひともご臨席賜りたく、心よりお待ち申し上げております。
この節は大変申し訳ありませんが、ご多用中(ごたようちゅう)とは存じますが、ご結婚の御祝儀(ごしゅうぎ)をどうぞよろしくお願い申し上げます。
例文2: 挨拶の例文
ご足労(ごそくろう)いただき、誠にありがとうございます。
この度の御婚礼(ごこんれい)にあたり、ご多忙中(ごたぼうちゅう)にもかかわらず、お目にかかる幸(さいわい)を頂き、心からお礼を申し上げます。
皆様のおかげで、私たちの結婚式はより一層の盛り上がりをみせることでしょう。
ご出席いただいた方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
まとめ:「結婚式」の昔の言い方
昔の言い方で「結婚式」とは、おめでたい日の儀式を指す言葉と言えます。
その当時は、今よりも厳かな雰囲気があり、これから新たな家庭を築くことへの祝福が込められていました。
昔の結婚式では、新郎新婦が正装や華美な衣装を身にまとい、家族や親しい人々が集まりました。
場所は教会や神社、寺院など、宗教的な要素を取り入れることが一般的でした。
新郎新婦はお互いの手を取り、誓いの言葉を交わすシーンは、感動的で心に響きます。
また、指輪の交換や花束の贈呈など、大切な瞬間がありました。
披露宴では、ゲストにおもてなしをするために、料理や飲み物が振る舞われました。
ケーキカットや乾杯の音頭を取るなど、一体感のあるイベントが行われました。
昔の結婚式は、家族や友人が力を合わせて準備し、思い出に残る一日を作り上げました。
お祝いの言葉や笑顔が絶えない、温かな雰囲気が特徴です。
結婚式のスタイルや形式は時代とともに変化していますが、昔の言い方であった「結婚式」は、大切な人との絆を深める日の儀式として、今もなお愛されています。
結婚式は、新たな人生の始まりを祝福し、幸せへの門出を迎える特別な瞬間です。