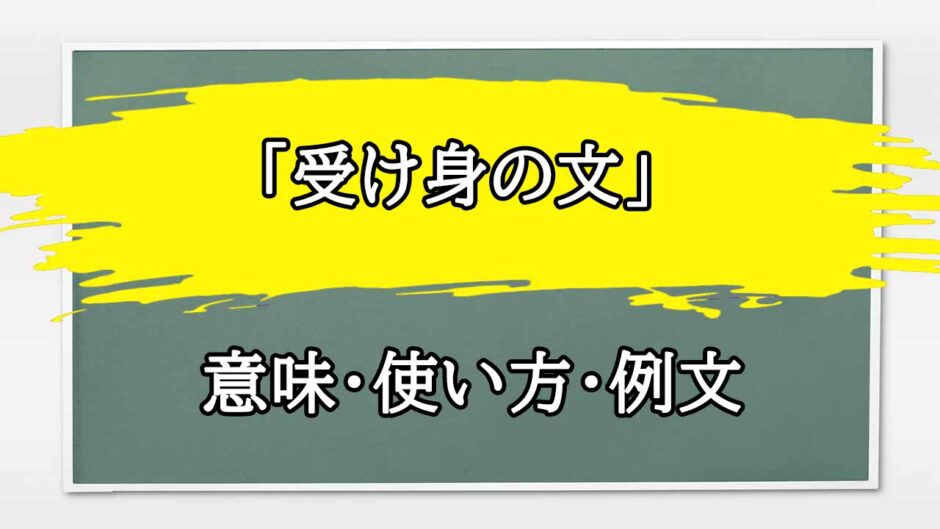受け身の文とは、日本語の文法の一つであり、主語が行為の受け手となる文のことを指します。
この文法形式は、行為の主体が明確でない場合や、行為が受け手によって行われる場合に使用されます。
日本語の特性を活かした表現方法であり、より柔軟な文章構造を作ることができます。
本記事では、受け身の文の意味や使い方について詳しく紹介させて頂きます。
受け身の文の特徴や形成方法、使い所などについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
それでは詳しく紹介させて頂きます。
「受け身の文」の意味と使い方
受け身の文の意味について
受け身の文は、主語が動作の受け手であることを表す文のことを指します。
受け身の文では、主語が動詞の受け身形で表現されます。
この形式では、主語が何かに対して行われる動作や状態を受ける役割を持ちます。
受け身の文は、日本語の文法において一般的に使用され、様々な場面で利用される重要な文法パターンと言えます。
受け身の文の使い方について
受け身の文は、以下のような場面で使用されます。
1. 行為の受け手を強調する場合:例えば、「この本はたくさんの人に読まれています」という文では、主語として「この本」が置かれていますが、実際の動作の受け手は「たくさんの人」です。
このように、受け身の文を使用することで、行為の受け手を強調することができます。
2. シンプルな表現を好む場合:受け身の文は、他の文法パターンと比較してシンプルな形式を持っています。
そのため、文章を簡潔に表現する際に受け身の文を使用することがあります。
3. 具体的な動作主が不明な場合:時には、具体的な動作主が不明な場合に受け身の文を使用することがあります。
例えば、「その窓は割られました」という文では、誰が窓を割ったのかが明確ではありませんが、窓が割られたという事実を表現するために受け身の文が使用されています。
以上のように、受け身の文はさまざまな場面で使用される文法パターンです。
理解して適切に使用することで、自然な日本語表現を作り出すことができます。
受け身の文の間違った使い方の例文とNG部分の解説
NG例文1:
本当に面白い映画が私によって見られました。
NG部分の解説:
「私によって」という表現は不自然です。
受け身の文では、動作を行う主体が「by」で示されることが一般的です。
したがって、「私によって」ではなく、「私によって見られた」という形で使うべきです。
NG例文2:
この部屋は毎日掃除によってきれいにされる。
NG部分の解説:
「掃除によって」という表現は不適切です。
受け身の文の目的語と作成者を示す語句は、一般的に「by」を使って表されます。
したがって、「掃除によってきれいにされる」ではなく、「掃除によってきれいにされる」という形で使うべきです。
NG例文3:
この報告書は私によって書かれた。
NG部分の解説:
「私によって」という表現は適切ではありません。
受け身の文では、作成者を示す語句は一般的に「by」で表されます。
したがって、「私によって書かれた」ではなく、「私によって書かれた」という形で使うべきです。
受け身の文の5つの例文と書き方のポイント解説
例文1:
例文:
彼女に手紙が届けられました。
書き方のポイント解説:
この句では、動作の主体が書かれていないため、受け身の文となります。
受け身の文では、対象が何らかの行動を受ける側として表現されます。
この例文では、「彼女」が「手紙が届けられる」という行動を受けている状況を表しています。
例文2:
例文:
この部屋は毎日掃除されています。
書き方のポイント解説:
「この部屋」が「毎日掃除される」という行動を受けているので、受け身の文となります。
受け身の文では、行動の主体が明示されていないことに注意しながら、対象が何らかの行動を受けている状況を表現します。
例文3:
例文:
昨日、雨に降られてびしょ濡れになりました。
書き方のポイント解説:
この句では、「昨日」が「雨に降られる」という行動を受けて、「びしょ濡れになる」という状態になっていることを表しています。
受け身の文では、行動の主体を省略しつつ、対象が何らかの行動や状態を受ける様子を表現します。
例文4:
例文:
その本は数カ国で翻訳されています。
書き方のポイント解説:
「その本」が「数カ国で翻訳される」という行動を受けているので、受け身の文となります。
受け身の文では、行動の主体を省略したまま、対象が何らかの行動を受ける状況を表現します。
例文5:
例文:
息子がパーティーで賞をもらわれました。
書き方のポイント解説:
この句では、「息子」が「パーティーで賞をもらう」という行動を受けている様子を表現しています。
受け身の文では、行動の主体が推測される場合でも、その主体を省略することが一般的です。
受け身の文についてまとめると、受け身の文は主語が行為を受ける形で表される文法構造です。
受け身の文は様々な場面で使用されますが、特に以下のような場合によく使われます。
第一に、行為の実行者が不明な場合や重要ではない場合に受け身の文が使われます。
第二に、行為の実行者を明示することで不必要な強調を避ける場合や、行為の実行者が自然に分かる文脈の中で受け身の文が使われます。
受け身の文の例をいくつか挙げると、例えば「彼はミスがされた」という文は、主語(彼)がミスを受けたことを表しています。
また、「この建物は毎日掃除されます」という文では、主語(この建物)が毎日掃除を受けることを表しています。
受け身の文は文章のバリエーションを広げるために重要な役割を果たします。
しかし、受け身の文を使う際には注意が必要です。
受け身の文を使うことで、主語が曖昧になったり、行為の実行者が不明瞭になったりすることがあります。
そのため、適切に受け身の文を使い、情報の伝達を明確にすることが重要です。
以上が、受け身の文についてのまとめです。
受け身の文は様々な場面で使用される文法構造であり、行為の受け手を表す役割を果たします。
適切に受け身の文を使い、情報の伝達を明確にすることが重要です。