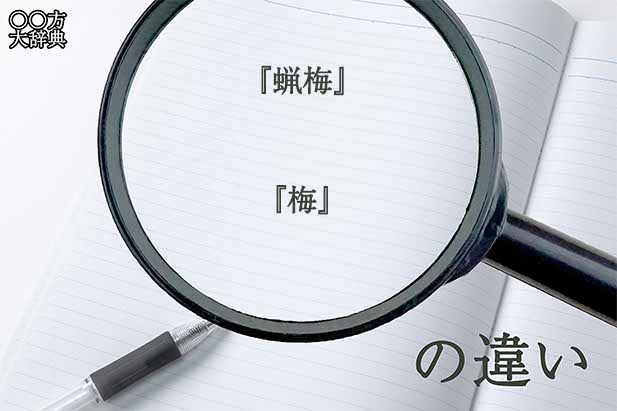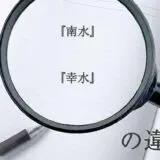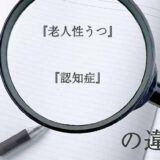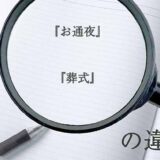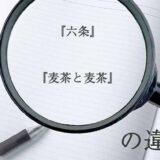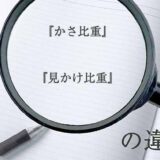この記事では『蝋梅』と『梅』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『蝋梅』の意味とは
蝋梅(ろうばい)は、1月から2月にかけて花が咲く落葉樹です。主に日本で見られる樹木で、白やピンク色の花を持つことが特徴です。蝋梅は冬に咲くため、寒さにも強く、その美しい花が雪景色と一緒に楽しめることから、冬の季節を彩る存在とされています。
類語・言い換えや詳細
1. ロウバイ
2. 冬桜
3. 雄木(オスジ)
4. 日本蝋梅
『梅』の意味とは
梅(うめ)は、1月から4月にかけて花が咲く落葉樹です。日本や中国に古くから栽培されており、白やピンク色の花を持つことが一般的です。梅の花は春の訪れを告げる有名な花として知られており、その美しい姿が多くの人々を魅了しています。
類語・言い換えや詳細
1. 梅宮(ウメノミヤ)
2. 白梅(シラウメ)
3. 赤梅(アカウメ)
4. プラム
『蝋梅』と『梅』の違いと使い方
蝋梅と梅は、花が似ていることがあり、見分けるのは難しいかもしれませんが、それぞれの違いや使い方には以下のような特徴があります。
1. 蝋梅は冬に咲くが、梅は春に咲く。
2. 蝋梅は寒さに強く、雪景色との相性が良いが、梅は春に咲く花であり、春の訪れを感じさせる。
3. 蝋梅は日本特有の花であり、日本文化と結びついているが、梅は日本や中国で見られる花であるとともに、古くから詩や絵画にも登場している。
まとめ
『蝋梅』と『梅』は、花の形や色が似ているが、それぞれに特徴や意味があります。蝋梅は冬の季節を彩り、梅は春の訪れを告げる美しい花です。どちらの花も日本文化や伝統に深く結びついており、季節の変化を感じさせる存在です。