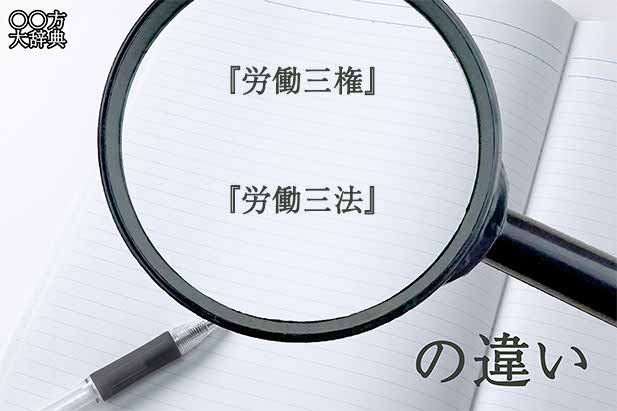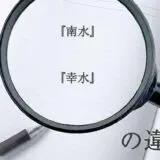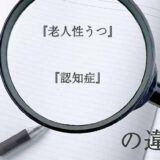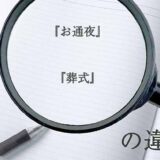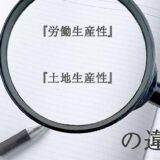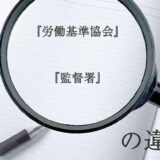この記事では『労働三権』と『労働三法』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『労働三権』の意味とは
労働三権とは、労働者が持つ権利のことを指します。具体的には、労働者団結権、団体交渉権、およびストライキ権の3つの権利を指します。労働者は、組織を作り団結し、労働条件の交渉や改善を行う権利を持っています。また、労働者は集団行動をとることで、労働条件や権益の実現を図るためにストライキを行う権利も持っています。
類語・言い換えや詳細
1. 労働者団結権 – 労働者が団結して組織を作る権利
2. 団体交渉権 – 労働者が団体として雇用主と交渉する権利
3. ストライキ権 – 労働者が集団行動をとるためにストライキを行う権利
『労働三法』の意味とは
労働三法とは、労働者の権利を保護し、労働環境を整備するための法律のことを指します。具体的には、労働基準法、労働安全衛生法、および労働者災害補償保険法の3つの法律を指します。これらの法律は、労働者の労働時間や休日、安全衛生の保護、労働災害の補償などを定めています。
類語・言い換えや詳細
1. 労働基準法 – 労働者の労働時間や休日などを定める法律
2. 労働安全衛生法 – 労働者の安全衛生を保護する法律
3. 労働者災害補償保険法 – 労働災害による補償を定める法律
『労働三権』と『労働三法』の違いと使い方
労働三権は労働者が持つ権利を指し、団結権、団体交渉権、およびストライキ権の3つの権利からなります。
一方、労働三法は労働者の権利を保護し労働環境を整備するための法律を指します。
労働三権は労働者の権利を行使するための権利であり、労働三法は労働環境を整備するための法律です。
まとめ
労働三権と労働三法は、それぞれ労働者の権利と労働環境を整備するための重要な概念です。
労働者は労働三権を行使し、団結し、ストライキを行うことで自らの権利を守ることができます。
また労働三法は労働者の労働条件の保護や安全衛生の確保を目的としているため、法律を遵守して労働環境を整備しましょう。