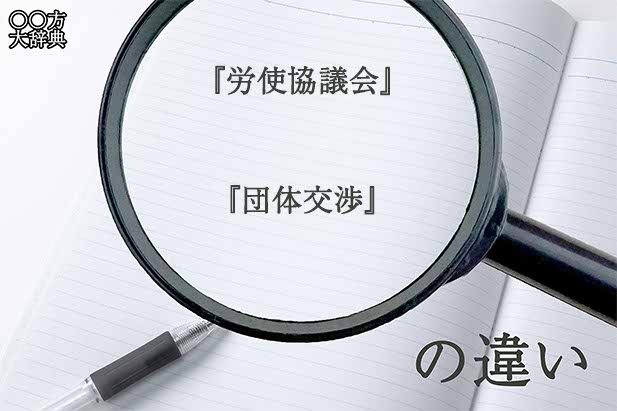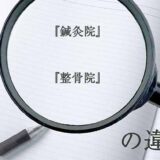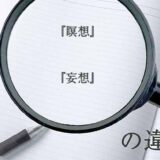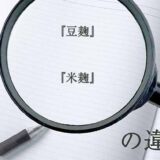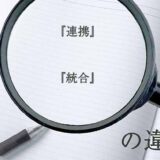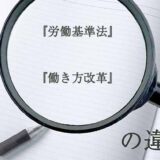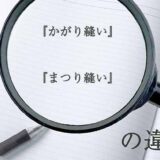この記事では『労使協議会』と『団体交渉』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『労使協議会』の意味とは
労使協議会とは、労働者側と雇用者側が労働関係に関する問題や労働条件の改善について話し合うために設立される組織のことです。労働組合の代表者や企業の経営者が参加し、双方の意見を交換して問題解決に取り組みます。
類語・言い換えや詳細
1. 労働者と雇用者が話し合うための組織
2. 労働条件の改善に関する問題解決を目的とする
3. 労働組合の代表者と企業の経営者が参加する
『団体交渉』の意味とは
団体交渉とは、労働者側の団体(労働組合)と雇用者側の団体(労働者団体や会社側の労使協議会)が労働条件や賃金などに関して交渉を行うことです。労使間の合意を目指して行われ、労働者団体の代表者や会社の経営陣が参加します。
類語・言い換えや詳細
1. 労働者団体と雇用者団体が交渉を行う
2. 労働条件や賃金に関する合意を目指す
3. 労働者団体の代表者と会社の経営陣が参加する
『労使協議会』と『団体交渉』の違いと使い方
労使協議会と団体交渉の違いは、参加者の組織が異なる点です。労使協議会では労働組合の代表者と企業の経営者が話し合いを行いますが、団体交渉では労働者団体と雇用者団体が交渉を行います。また、目的も異なります。労使協議会は労働条件の改善に関する問題解決を目指すのに対し、団体交渉は労働条件や賃金に関する合意を目指します。
使い方としては、労働条件の改善や問題解決に取り組む場合には労使協議会を利用し、労働条件や賃金に関する合意を目指す場合には団体交渉を行います。
まとめ
労使協議会と団体交渉は、労働関係における問題解決や合意形成のために用いられる手段です。労働者と雇用者が相互に意見を交換し、労働条件や賃金の改善に取り組むことで、より良い労働環境を実現します。労使協議会と団体交渉の違いを理解し、適切な場面で利用していきましょう。