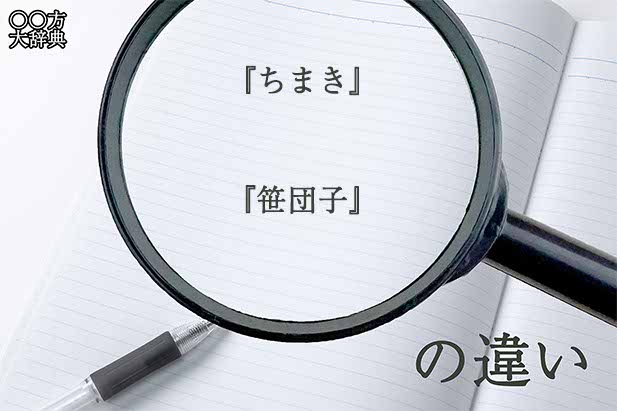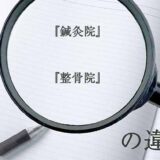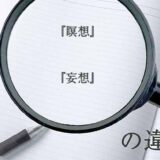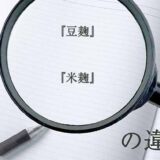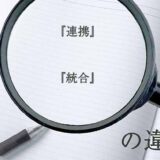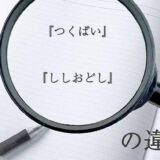この記事では『ちまき』と『笹団子』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『ちまき』の意味とは
『ちまき』は、日本の伝統的な食べ物であり、お米をもち米として炊き上げ、それを竹の皮で包んで作るものです。主に端午の節句や季節の行事で食べられることがあります。色々な具材や味付けが施されることもありますが、基本的にはもち米の食感と風味が特徴です。
類語・言い換えや詳細
1. もち米を使用する
2. 竹の皮で包む
3. 端午の節句や季節の行事で食べられる
4. 味付けや具材がさまざま
『笹団子』の意味とは
『笹団子』は、和菓子の一種であり、もち米を練り、それを笹の葉で包んで作るものです。主に夏の風物詩として知られており、夏祭りや行楽のお供として楽しまれます。笹の香りが特徴的で、もちもちとした食感があります。
類語・言い換えや詳細
1. もち米を使用する
2. 笹の葉で包む
3. 夏の風物詩として知られる
4. 夏祭りや行楽のお供になる
5. 笹の香りが特徴的
『ちまき』と『笹団子』の違いと使い方
『ちまき』と『笹団子』の違いは、使われる包み材や食べられる季節が異なる点です。『ちまき』は竹の皮で包まれており、主に端午の節句や季節の行事に食べられます。一方、『笹団子』は笹の葉で包まれており、夏になると夏祭りや行楽のお供として楽しまれます。また、味付けや具材も違いがあり、『ちまき』はさまざまなバリエーションがありますが、『笹団子』は基本的には笹の香りが特徴で特定の味付けがされていることが多いです。
まとめ
『ちまき』と『笹団子』は、日本の伝統的な食べ物であり、それぞれ特徴があります。『ちまき』はもち米を竹の皮で包み、端午の節句や季節の行事に食べられます。一方、『笹団子』はもち米を笹の葉で包み、夏になると夏祭りや行楽のお供として楽しまれます。使い方や味付けも異なりますので、適切に使い分けましょう。