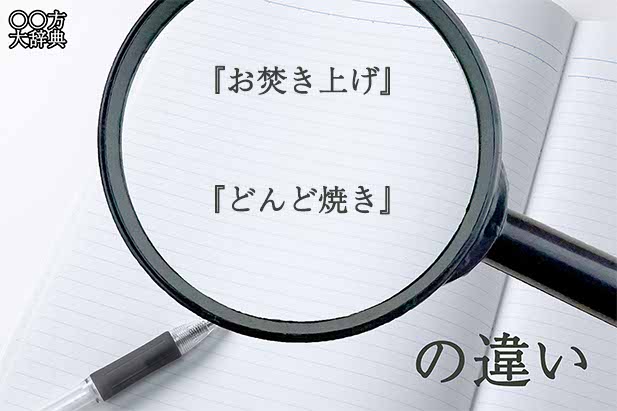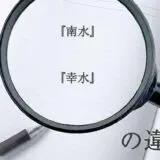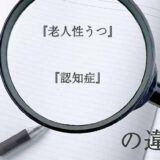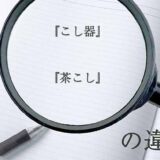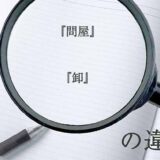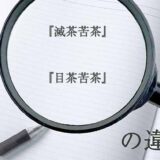この記事では『お焚き上げ』と『どんど焼き』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『お焚き上げ』の意味とは
『お焚き上げ』とは、神社や仏教寺院で行われる儀式や祭りの一つです。主に、先祖の霊を供養する目的で行われることが多いです。焚き火を使って、木や紙などの物を燃やし、その煙や火の力を通じて、故人の霊を天に送ると考えられています。
類語・言い換えや詳細
1. お骨の埋葬前に行われることが多い儀式です。
2. 大切な先祖を思い、感謝の気持ちを込めて行います。
3. 焚き火の煙が霊魂を導く役割があると信じられています。
『どんど焼き』の意味とは
『どんど焼き』とは、寺社の境内や町内で行われる古くからの風習です。主に、新年の終わりや節分の頃に行われます。不浄なものや厄災を一掃するために、穢れを焼き尽くすことを目的としています。
類語・言い換えや詳細
1. 節分の前に行われ、豆まきと共に厄を祓う行事です。
2. 積年の厄災や災厄を一掃する意味があります。
3. ホームパーティーやイベントとしても楽しまれています。
『お焚き上げ』と『どんど焼き』の違いと使い方
『お焚き上げ』と『どんど焼き』の違いは、主な目的と行われる場所にあります。『お焚き上げ』は、先祖の霊を供養するために行われ、主に神社や仏教寺院で行われます。『どんど焼き』は、不浄なものや厄災を一掃するために行われ、寺社の境内や町内で行われることが多いです。
また、使い方では『お焚き上げ』は、先祖を思い、感謝の気持ちを込めて行います。一方、『どんど焼き』は、節分の前に行われ、豆まきや厄払いの行事に組み込まれることが多いです。
まとめ
『お焚き上げ』と『どんど焼き』は、それぞれ異なる目的や行われる場所を持ちます。『お焚き上げ』は、先祖の霊を供養するために行われる儀式であり、『どんど焼き』は、穢れや厄災を一掃するために行われる風習です。しっかりとその意味と使い方を理解し、適切な場面で使い分けましょう。