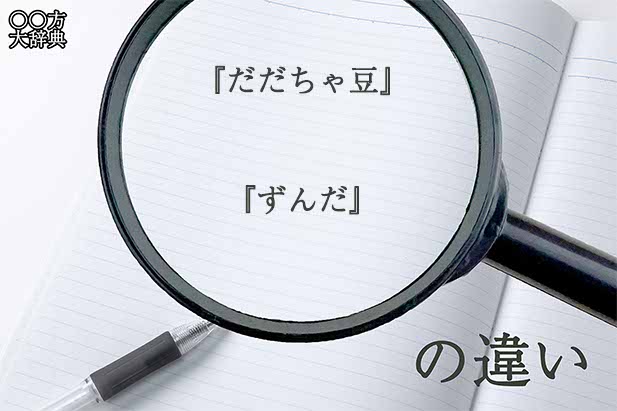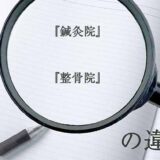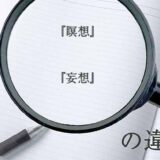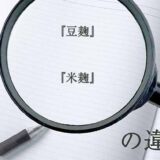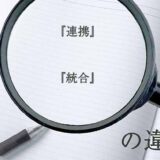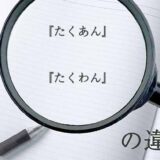この記事では『だだちゃ豆』と『ずんだ』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『だだちゃ豆』の意味とは
『だだちゃ豆』は、関西地方で使われる方言で、日本語では「青大豆」を指します。色が濃くて独特の風味があり、茹でたり炒めたりして食べることができます。
類語・言い換えや詳細
1. 青大豆
2. 豆の一種
3. 関西方言で使われる
『ずんだ』の意味とは
『ずんだ』は、青大豆をすり潰して作った独特のペースト状の食品です。主に東海地方や関東地方で使われ、餅やパン、アイスクリームのトッピングとして使われることがあります。
類語・言い換えや詳細
1. 青大豆をすり潰したペースト
2. 主に東海地方や関東地方で使われる
3. 餅やパン、アイスクリームなどに使われる
『だだちゃ豆』と『ずんだ』の違いと使い方
『だだちゃ豆』と『ずんだ』の違いは、食べ方や用途にあります。『だだちゃ豆』は、茹でたり炒めたりしてそのまま食べることができますが、『ずんだ』はすり潰してペースト状にしたもので、餅やパン、アイスクリームのトッピングとして使われることが一般的です。
類語・言い換えや詳細
1. 『だだちゃ豆』はそのまま食べることができるが、『ずんだ』はトッピングとして使われる
2. 『だだちゃ豆』は茹でたり炒めたりして食べるが、『ずんだ』はすり潰してペースト状にする
まとめ
『だだちゃ豆』は関西方言で使われる青大豆で、茹でたり炒めたりして食べることができます。一方、『ずんだ』は青大豆をすり潰して作られたペースト状の食品で、餅やパン、アイスクリームのトッピングとして使われます。それぞれの違いを理解して、適切に使い分けましょう。