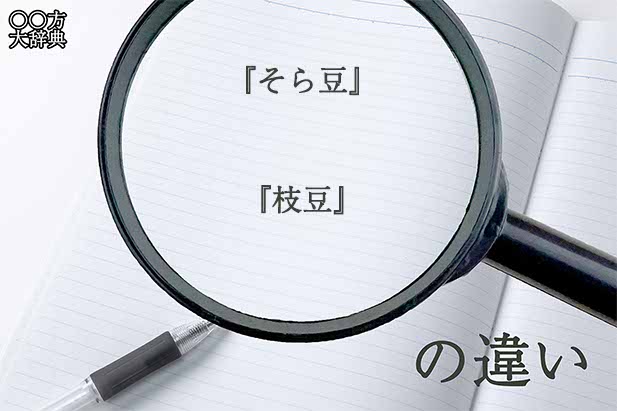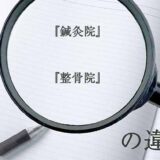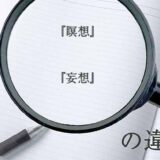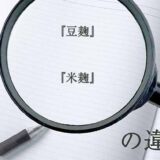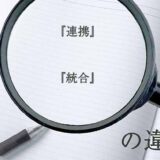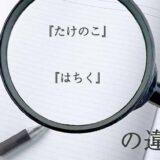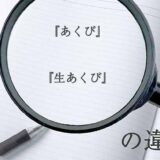この記事では『そら豆』と『枝豆』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『そら豆』の意味とは
『そら豆』とは、豆科の植物で、その若い実を食べることができます。一般的には、豆の仲間ではありますが、『そら豆』はそのまま食べられるタイプの種類のことを指します。
類語・言い換えや詳細
1. 日本では古くから栽培されてきた野菜であり、夏になると丸々とした莢(ひさし)をつけます。
2. 青々とした色合いとしゅわっとした食感が特徴で、塩茹でや煮物としてよく食べられます。
3. そら豆は、栄養価が高く、たんぱく質や食物繊維、ビタミンC、カリウムなどが豊富に含まれています。
『枝豆』の意味とは
『枝豆』は、大豆の実が未熟な状態のものを指します。言い換えれば、大豆の豆莢が緑色のままのものが枝豆です。
類語・言い換えや詳細
1. 枝豆は主に夏季に収穫され、日本の夏の風物詩の一つとされています。
2. 茹でたり蒸したりして食べられることが一般的であり、縁日や居酒屋などでもよく提供されます。
3. 枝豆は、大豆に比べて低カロリーでありながら、たんぱく質や食物繊維、ビタミンE、鉄などの栄養素を含んでいます。
『そら豆』と『枝豆』の違いと使い方
『そら豆』と『枝豆』の違いは、まず豆の種類が異なります。『そら豆』はシロマメ科の植物であり、一般的には生でそのまま食べることができます。一方、『枝豆』は大豆の実が未熟な状態のものを指し、茹でたり蒸したりして食べます。
また、使い方としては、『そら豆』はそのまま食べるほかにも、塩茹でや煮物として使われます。一方、『枝豆』は茹でて塩を振ったり、バターやソースをつけて食べることが一般的です。
まとめ
『そら豆』と『枝豆』は一見似ていますが、豆の種類や食べ方に違いがあります。『そら豆』はそのまま食べたり、料理に使ったりすることができ、『枝豆』は茹でて塩やソースをつけて食べたりします。食材としての特徴や栄養価も異なるので、使う際は適切に使い分けましょう。