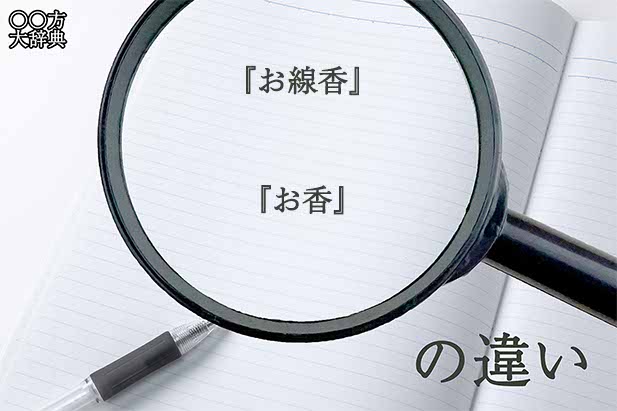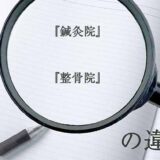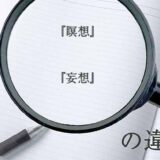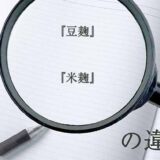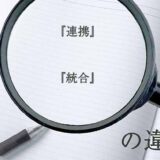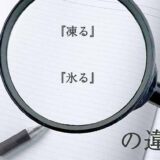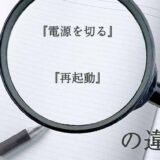この記事では『お線香』と『お香』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『お線香』の意味とは
『お線香』とは、日本の伝統的な香り付けのための道具です。主に葬儀や仏事で使用され、亡くなった人への供養や祭りの際に使われます。お線香は細長い形状をしており、火を点けて燃やすことによって香りを出します。
類語・言い換えや詳細
1. 高温で燃焼する特徴があります。
2. 香りや煙がたち、祭壇や供養所で使われます。
3. 火をつけることで香りが発生します。
4. 祈りや思いを込めて使用されることが多いです。
『お香』の意味とは
『お香』は、主に日本や中国で使用される伝統的な香り付けのための道具です。主な使用法は瞑想やリラックス効果を得るための香りです。粉末や固形の形状をしており、特定の材料を混ぜて作られます。
類語・言い換えや詳細
1. 低温で燃焼する特徴があります。
2. 瞑想やリラックス効果が期待されて使用されます。
3. 無煙であることが多く、煙が立ちにくいです。
4. 香り付けのためだけでなく、インテリアとしても使用されることもあります。
『お線香』と『お香』の違いと使い方
『お線香』と『お香』の違いは、主に使用される場面と香りの特徴にあります。
・『お線香』は高温で燃焼し、祭りや供養の場で使われることが多いです。また、燃える音や煙が立ち、一時的な香りを楽しむことができます。
・一方、『お香』は低温で燃焼し、瞑想やリラックス効果を得るための香りとして使用されます。無煙であり、長時間香りが持続します。
使い方も異なります。『お線香』は直接燃やし、祭壇や供養所に置くことが多いです。一方、『お香』は専用の容器や香炉に入れ、少量ずつ焚くことが一般的です。
まとめ
『お線香』と『お香』は香り付けのために使用される道具ですが、使われる場面や香りの特徴が異なります。祭りや供養の場では『お線香』を使用し、瞑想やリラックス効果を得る際には『お香』を使用することが一般的です。しっかりと使い分けて、香りを楽しんでください。