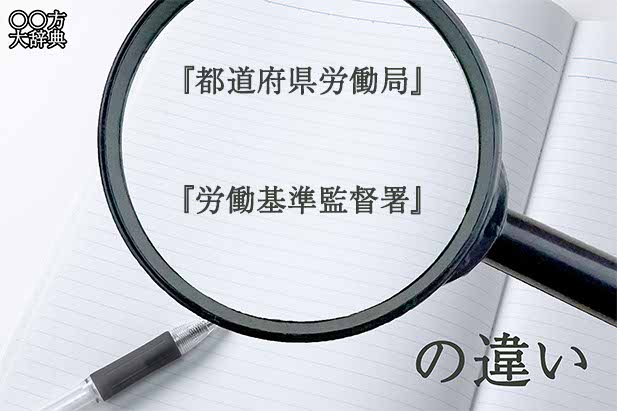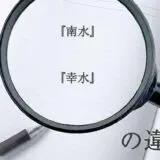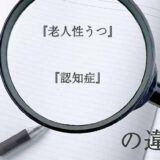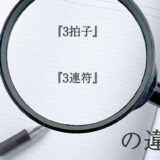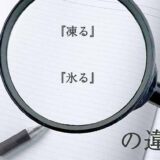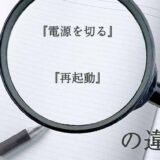この記事では『都道府県労働局』と『労働基準監督署』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『都道府県労働局』の意味とは
都道府県労働局とは、各都道府県に設置されている公的な機関です。労働関連の法律や政策に関する情報提供や助言、相談窓口などを担当しています。具体的な業務内容としては、労働条件の監督や助言、就職・職業紹介に関する支援、雇用情報の提供などがあります。
類語・言い換えや詳細
1. 労働関連の法律や政策に関する情報提供
2. 労働条件の監督や助言
3. 就職・職業紹介に関する支援
4. 雇用情報の提供
『労働基準監督署』の意味とは
労働基準監督署は、国の中央省庁である厚生労働省の外局です。労働基準法や労働関連法の遵守や労働基準の監督、労働紛争の仲裁などを担当しています。具体的な業務内容としては、労働時間や賃金の遵守の監督、労働条件の改善や解決の支援、労働紛争の仲裁などがあります。
類語・言い換えや詳細
1. 労働基準法や労働関連法の遵守の監督
2. 労働時間や賃金の遵守の監督
3. 労働条件の改善や解決の支援
4. 労働紛争の仲裁
『都道府県労働局』と『労働基準監督署』の違いと使い方
都道府県労働局と労働基準監督署は、役割や所属する機関が異なりますが、労働者の権益保護や労働条件の遵守を目的としています。労働関連の法律や労働基準の遵守に関する監督や支援を必要とする場合は、問題が発生する地域ごとに都道府県労働局に相談や助言を求めることが適切です。一方、厳しい労働条件や権益を侵害された場合は、労働基準監督署に連絡をすることが重要です。目的や問題によって適切な機関を選び、利用することが大切です。
まとめ
都道府県労働局と労働基準監督署は、労働関連の問題や労働条件の遵守に関する機関です。都道府県労働局は各地域の相談や助言に特化し、労働基準監督署は労働条件の遵守や紛争の解決に力を入れています。適切な機関を選び、労働者の権益保護や労働条件の改善に積極的に活用しましょう。