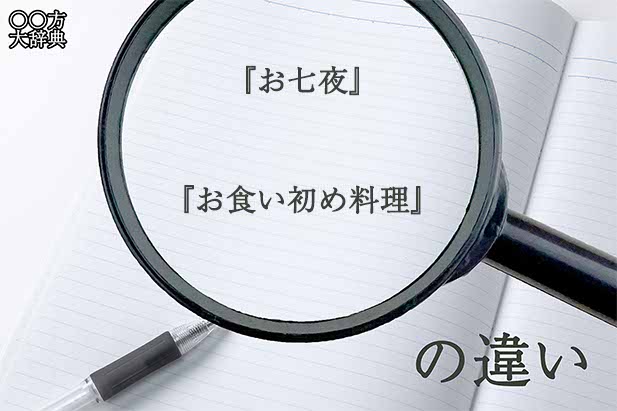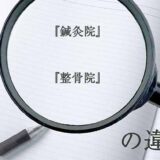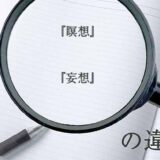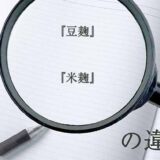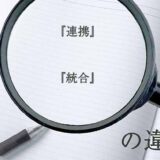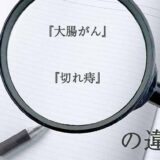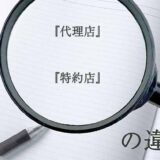この記事では『お七夜』と『お食い初め料理』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『お七夜』の意味とは
『お七夜』は、日本の独自のお祝いの一つで、生後七日目の赤ちゃんを家族や親しい人たちと一緒に祝う儀式です。この儀式では、赤ちゃんへの祝福や成長を願う気持ちを表し、家族や親しい人たちが集まり、お祝いの食事を楽しみます。
類語・言い換えや詳細
1. 生後七日目の赤ちゃんを祝うお祝いの儀式
2. 赤ちゃんへの祝福や成長を願う
3. 家族や親しい人たちが集まり、お祝いの食事を楽しむ
『お食い初め料理』の意味とは
『お食い初め料理』は、日本の伝統的な行事で、赤ちゃんが初めてご飯を食べる様子を祝う儀式です。この儀式では、家族や親しい人たちが集まり、特別な料理を用意し、赤ちゃんが元気にご飯を食べられるように願いながら祝います。
類語・言い換えや詳細
1. 赤ちゃんが初めてご飯を食べる瞬間を祝う儀式
2. 家族や親しい人たちが集まって行う
3. 特別な料理を用意し、赤ちゃんの成長を願う
『お七夜』と『お食い初め料理』の違いと使い方
『お七夜』と『お食い初め料理』の違いは、祝うタイミングと儀式の内容です。『お七夜』は生後七日目の赤ちゃんを祝う儀式で、家族や親しい人たちが集まりお祝いの食事を楽しむことが主な特徴です。一方、『お食い初め料理』は赤ちゃんが初めてご飯を食べる瞬間を祝う儀式で、家族や親しい人たちが集まって特別な料理を用意し、赤ちゃんの成長を願います。使い方では、赤ちゃんが生後七日目の場合は『お七夜』、赤ちゃんが初めてご飯を食べる場合は『お食い初め料理』と使い分けることが一般的です。
まとめ
『お七夜』と『お食い初め料理』は、赤ちゃんの成長を祝う日本の伝統的な行事です。『お七夜』は生後七日目の赤ちゃんを祝い、お祝いの食事を楽しむ儀式です。一方、『お食い初め料理』は赤ちゃんが初めてご飯を食べる瞬間を祝う儀式で、特別な料理を用意して赤ちゃんの成長を願います。使い方では、赤ちゃんの年齢や成長の節目に合わせて使い分けましょう。