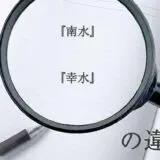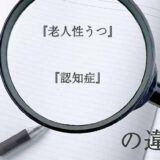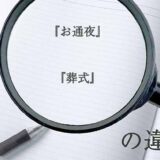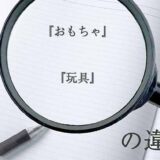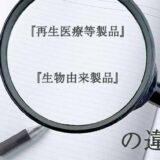この記事では『祭主』と『斎主』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『祭主』の意味とは
『祭主』とは、祭りや行事の主催者や主導者を指す言葉です。祭りや行事の準備や実施を監督し、参加者に従事する役割を果たします。祭主は、祭りや行事の計画立案や予算管理、参加者やスタッフの調整など、さまざまな責任を持ちます。
類語・言い換えや詳細
1. 儀式や行事の主催者
2. 参加者の調整とイベントの計画立案
3. 予算管理とイベントの準備
『斎主』の意味とは
『斎主』は、神職や僧侶などが宗教的な儀式や祭りにおいて主導する役割を指す言葉です。特に、神社や寺院で行われる祭りや法要などで、儀式の進行や祈祷を行い、参加者のために神聖な場を提供します。斎主は、神職や僧侶としての教育や訓練を受け、宗教行事の執行に携わります。
類語・言い換えや詳細
1. 宗教的な儀式や祭りの主導者
2. 神職や僧侶としての教育や訓練を受ける
3. 儀式の進行と祈祷を行う
『祭主』と『斎主』の違いと使い方
『祭主』と『斎主』の違いは、役割と関連しています。祭主は祭りや行事の主催者であり、イベント全体を監督します。一方、斎主は宗教的な儀式や祭りの主導を担当し、参加者に神聖な経験を提供します。使い方では、祭主は宴会や祭り、行事などの主催者を指す場合に使用されます。一方、斎主は神社や寺院などの宗教的な場で、儀式や法要などを執り行う際に使用されます。
まとめ
『祭主』と『斎主』はそれぞれ異なる役割を担い、異なる場面で使用されます。祭主は祭りや行事の主催者として、計画立案や参加者の調整を行います。一方、斎主は宗教的な儀式や祭りにおいて主導し、祈祷や祝福を行います。正確に使い分けることで、適切な場面で適切な役割を果たすことができます。