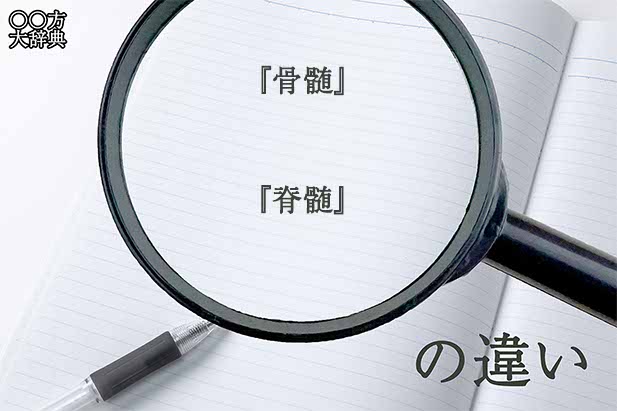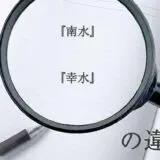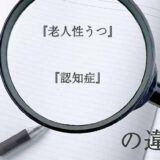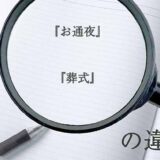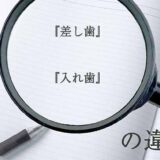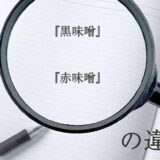この記事では『骨髄』と『脊髄』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『骨髄』の意味とは
骨髄(こつずい)とは、骨の中に存在する柔らかい組織のことです。骨自体は硬い物質でできていますが、その内部には骨髄が詰まっています。骨髄には造血幹細胞が含まれており、血液や免疫細胞の生成に重要な役割を果たしています。また、骨髄から採取した幹細胞は、移植などの医療にも利用されています。
類語・言い換えや詳細
1. 骨の中にある柔らかい組織
2. 造血幹細胞が含まれている
3. 血液や免疫細胞の生成に関与している
『脊髄』の意味とは
脊髄(せきずい)とは、脊柱の中にある中枢神経組織の一部です。脳からの神経信号を体の各部に伝える役割を持っており、身体の運動や感覚、内臓の調整などに関与しています。脊髄は脳と連絡している重要な経路であり、脊髄の損傷は麻痺や感覚の障害などを引き起こすことがあります。
類語・言い換えや詳細
1. 脊柱の中にある中枢神経組織の一部
2. 神経信号を体の各部に伝える
3. 身体の運動や感覚、内臓の調整に関与している
『骨髄』と『脊髄』の違いと使い方
『骨髄』と『脊髄』は外見や役割、使い方などにおいて異なる点があります。
1. 外見:『骨髄』は骨の中に存在し、柔らかい組織であるのに対し、『脊髄』は脊柱の中にある中枢神経組織です。
2. 役割:『骨髄』は血液や免疫細胞の生成に関与しており、幹細胞の移植などにも利用されます。一方、『脊髄』は脳からの神経信号を体の各部に伝える役割を担っています。
3. 使い方:『骨髄』は骨髄バンクや骨髄提供などの表現で使われることがあります。一方、『脊髄』は脊髄損傷や脊髄反射などの表現で使われます。
まとめ
『骨髄』は骨の中に存在し、血液や免疫細胞の生成に関与しています。一方、『脊髄』は脊柱の中にある中枢神経組織であり、脳からの神経信号を体の各部に伝える役割を持っています。それぞれの使い方や表現を理解し、正しく使い分けましょう。