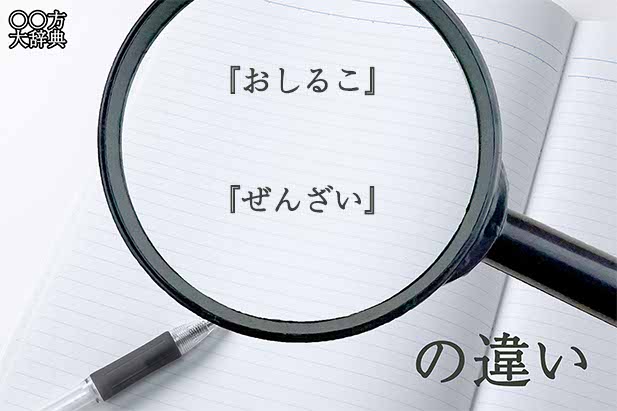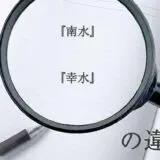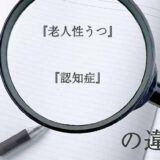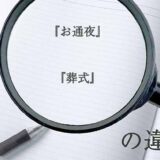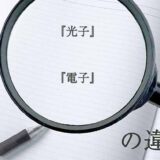この記事では『おしるこ』と『ぜんざい』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『おしるこ』の意味とは
『おしるこ』は、日本の伝統的な甘味料理であり、お正月や季節の行事などでよく食べられます。主な材料は、あずき(小豆)、砂糖、水です。あずきを煮込んで砂糖で甘く炊き上げたものであり、滑らかな食感と甘さが特徴です。
類語・言い換えや詳細
1. あずきを煮込んで炊き上げる
2. 砂糖で甘くする
3. 滑らかな食感と甘さが特徴
『ぜんざい』の意味とは
『ぜんざい』もまた、日本の伝統的な甘味料理であり、主に夏に食べられます。主な材料は、もち米(うるち米)、あんこ(餡子)、砂糖、水です。もち米を煮て甘く炊き上げ、あんこをのせることで、もちもちした食感と甘さが楽しめます。
類語・言い換えや詳細
1. もち米を煮込んで炊き上げる
2. あんこをのせる
3. もちもちした食感と甘さが楽しめる
『おしるこ』と『ぜんざい』の違いと使い方
『おしるこ』と『ぜんざい』の違いは、主に材料と季節にあります。『おしるこ』はあずきが主な材料であり、お正月などの冬季の行事でよく食べられます。一方、『ぜんざい』はもち米が主な材料であり、夏に涼しい季節によく食べられます。どちらも甘味料理であり、滑らかな食感ともちもちした食感が特徴です。
類語・言い換えや詳細
1. 材料に違いがある(あずき vs もち米)
2. 食べる季節が違う(冬季 vs 夏季)
3. 共通して甘味料理であり、滑らかな食感ともちもちした食感が特徴
まとめ
『おしるこ』と『ぜんざい』は日本の伝統的な甘味料理であり、それぞれ特徴があります。『おしるこ』はあずきが主な材料であり、冬季の行事で食べられます。一方、『ぜんざい』はもち米が主な材料であり、夏に食べることが多いです。どちらも甘さと食感が特徴的で、その違いを理解しながら楽しんでください。