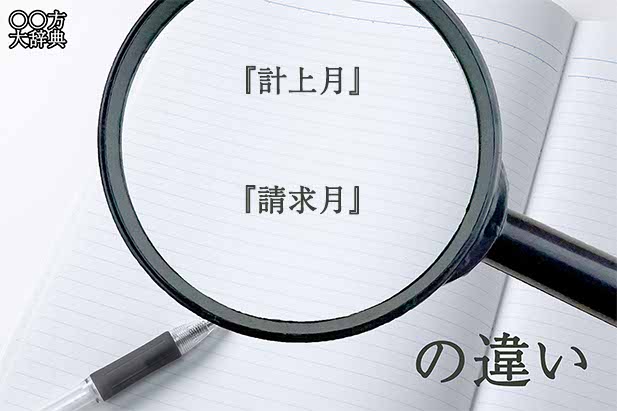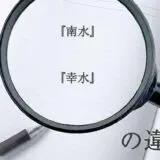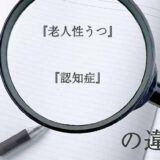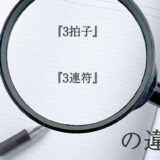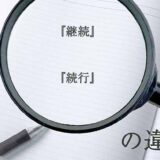この記事では『計上月』と『請求月』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『計上月』の意味とは
『計上月』とは、会計の仕組みで使用される言葉であり、企業や組織が販売した商品やサービスの売上高を計上するための月を指します。具体的には、売上データを集計して各部門や会計部に情報を提供するために使用されます。『計上月』は、売上が実際に行われた月ではなく、売上データの処理や分析に使用される月を指します。
類語・言い換えや詳細
1. 売上データを集計するための月
2. 売上高を計上するための月
3. 会計処理や分析に使用される月
『請求月』の意味とは
『請求月』とは、請求書を送付するための月を指します。企業や組織が顧客に対して商品やサービスの代金を請求する際に、請求書の発行月を指します。具体的には、商品やサービスの提供が行われ、顧客に代金の支払いを求めるための請求書が発行される月を指します。
類語・言い換えや詳細
1. 請求書を送付するための月
2. 代金の支払いを求めるための月
『計上月』と『請求月』の違いと使い方
『計上月』と『請求月』の違いは、主に目的となる月が異なる点です。『計上月』は売上データの処理や分析に使用される月であり、会計の視点からの月の選定です。一方『請求月』は請求書の発行月であり、支払いの管理や顧客とのやり取りに関係する月です。具体的には、『計上月』は会計部門や部門間での情報共有や経営判断に使用されますが、『請求月』は顧客との取引や債権管理に使用されます。
例えば、ある商品を1月に販売した場合、『計上月』は1月ですが、『請求月』は2月となります。このように、売上が実際に行われた月と請求書の発行月が異なる場合があります。
まとめ
『計上月』と『請求月』は会計や経営管理において重要な概念です。『計上月』は売上データの集計や会計処理に関わり、『請求月』は請求書の発行や代金の管理に関わります。両者の違いと使い方を理解することで、組織や企業の運営において正確な情報の把握や円滑な取引が行えるようになります。