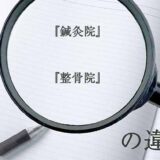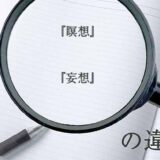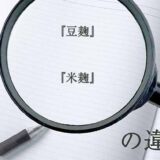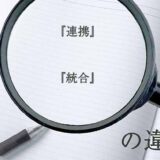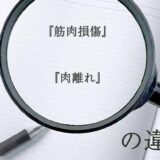この記事では『おこわ』と『赤飯』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『おこわ』の意味とは
『おこわ』は、日本の伝統的な料理の一つであり、白米に具材を混ぜて蒸したものです。主にお祭りや特別な行事の時に食べられることが多いです。食べ物として提供される場合には、おしるこや漬物などと一緒に食べられることが一般的です。
類語・言い換えや詳細
1. 米を蒸している
2. 具材を混ぜている
3. 特別な行事の時に食べられることが多い
4. おしるこや漬物と一緒に食べられることが一般的
『赤飯』の意味とは
『赤飯』は、米と紅花などの材料で赤く染めたもち米のことを指します。主にお祝いごとやお正月の料理として知られています。食べる際には、塩や味噌汁と一緒に食べられることが一般的です。
類語・言い換えや詳細
1. もち米を赤く染めている
2. お祝いごとやお正月の料理として知られている
3. 塩や味噌汁と一緒に食べられることが一般的
『おこわ』と『赤飯』の違いと使い方
『おこわ』と『赤飯』は、どちらも米を主成分とした料理ですが、いくつかの点で違いがあります。まず、見た目の違いですが、『おこわ』は普通の白い色をしており、『赤飯』は赤く染められています。また、味や食べ方にも違いがあります。『おこわ』は具材と一緒に蒸しているため、具材の風味を楽しむことができます。一方、『赤飯』はもち米を赤く染めることで独特の風味があり、そのまま食べることが一般的です。
『おこわ』と『赤飯』の使い方については、主に特別な行事やお祭りの際に使われることが多いです。また、地域によっても使い方が異なる場合もありますので、地域の習慣や文化に合わせて使い分けることが大切です。
まとめ
『おこわ』と『赤飯』は、日本の伝統的な料理であり、それぞれ独自の特徴や使い方があります。『おこわ』は具材と一緒に蒸されており、おしるこや漬物と一緒に食べられることが一般的です。一方、『赤飯』はもち米を赤く染めており、塩や味噌汁と一緒に食べられることが一般的です。どちらの料理も特別な行事やお祭りの際に食べることが多く、地域の習慣や文化によって使い分けられます。しっかりと使い方を理解し、おいしい料理を楽しんでください。