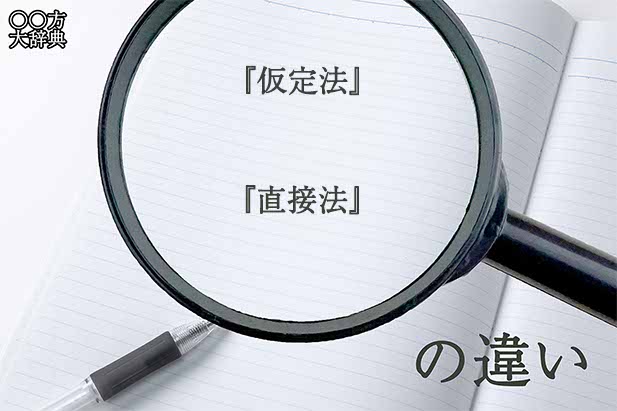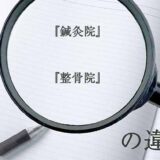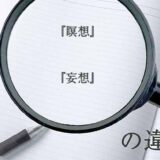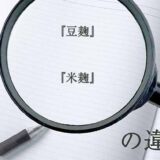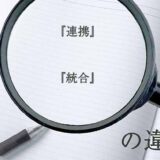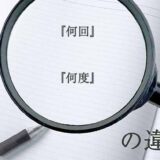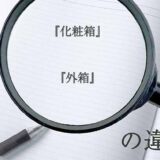この記事では『仮定法』と『直接法』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『仮定法』の意味とは
仮定法は、実際には起こっていない状況や事実を仮定して話す文法形式です。主に「もし~ならば」という条件を表現する際に使います。例えば、「もし天気が良ければ、ピクニックに行く」という文は仮定法の形式です。
類語・言い換えや詳細
1. たとえば
2. もし?なら
3. もし?だったら
4. もし?ならば
5. 仮に?とすると
『直接法』の意味とは
直接法は、実際に現実の状況や事実を述べる文法形式です。主に日常会話や報道などで使われます。例えば、「私は明日休みです」という文は直接法の形式です。
類語・言い換えや詳細
1. ?と言う
2. ?と思う
3. ?と書く
4. ?と答える
5. ?と説明する
『仮定法』と『直接法』の違いと使い方
仮定法と直接法の違いは、話し手の意図や言いたいことが異なります。仮定法は仮定や条件を表現するために使われ、想像や仮定が含まれています。一方、直接法は実際の事実や状況を述べるために使われ、確かな情報を伝えます。
使い方のポイントは、話し手の意図や言いたいことを考えることです。もし「もし~ならば」という条件を表現したい場合は仮定法を使い、現実の状況や事実を述べたい場合は直接法を使います。
まとめ
仮定法と直接法はそれぞれ異なる状況や意図を表現するために使われます。しっかりと使い分けることで、自分の意図を明確に相手に伝えることができます。日常会話や文章表現で使い方を意識して、正しく文を構成するようにしましょう。