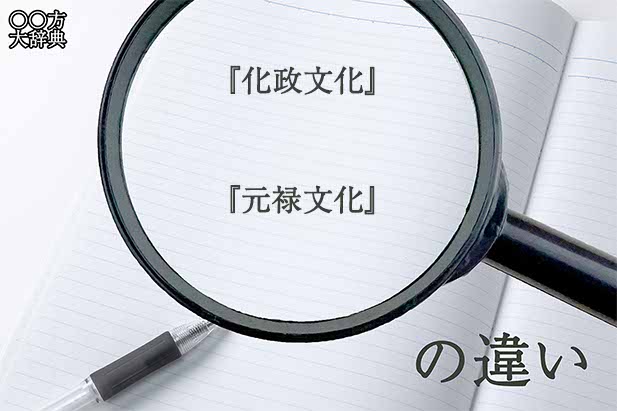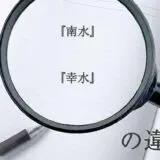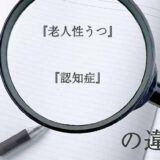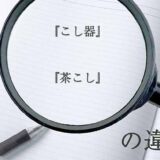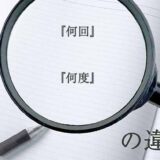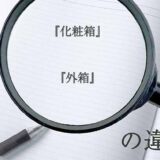この記事では『化政文化』と『元禄文化』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『化政文化』の意味とは
『化政文化』とは、江戸時代後期の文化のことを指します。この時代には、幕府の政策の変化や国内外の影響によって、秩序や様式が変化していきました。この時代の文化は、物事を合理的に考えることや知識を重視する傾向があります。また、学問や芸術の発展が活発に行われ、多様な文化が生まれました。
類語・言い換えや詳細
1. 享保文化
2. 寛政文化
3. 文化文政期
4. 蛮社の獄
『元禄文化』の意味とは
『元禄文化』とは、江戸時代の元禄時代に栄えた文化のことを指します。この時代は、経済的な繁栄や都市の発展が進み、豪華で贅沢な文化が花開きました。特に、歌舞伎や浮世絵の発展、宴会や遊びの洗練されたスタイルなどが特徴です。また、この時代には蘭学の影響も広まりました。
類語・言い換えや詳細
1. 歌舞伎
2. 浮世絵
3. 茶道
4. 元禄風俗
『化政文化』と『元禄文化』の違いと使い方
『化政文化』と『元禄文化』は、時代や特徴が異なるため、使い方にも違いがあります。『化政文化』は、合理的で知識を重視する文化であり、学問や芸術の発展に重点が置かれています。一方、『元禄文化』は、豪華で贅沢な文化であり、歌舞伎や浮世絵の発展、宴会や遊びの洗練されたスタイルが特徴です。使い分ける際には、時代背景や文化の特徴を考慮しながら、適切な文脈で使用することが重要です。
まとめ
『化政文化』と『元禄文化』は、江戸時代の異なる時代に栄えた文化です。『化政文化』は合理的で知識を重視し、学問や芸術の発展が活発でした。一方、『元禄文化』は豪華で贅沢な文化であり、歌舞伎や浮世絵などが栄えました。使い分ける際には、それぞれの特徴と時代背景を考慮し、適切に使用することが大切です。