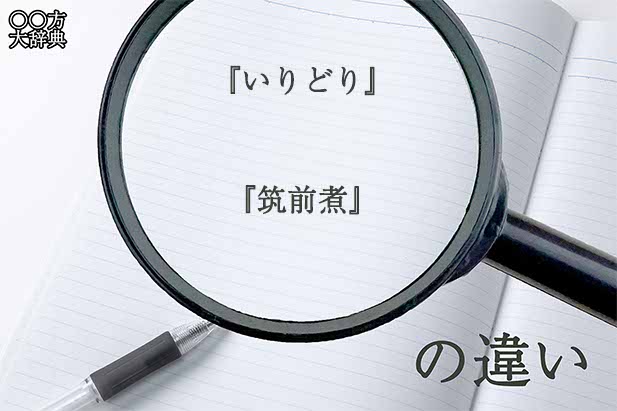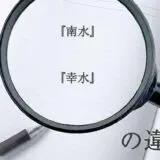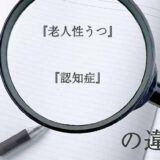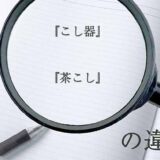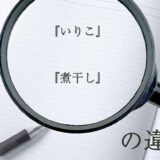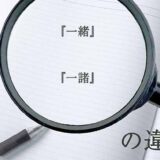この記事では『いりどり』と『筑前煮』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『いりどり』の意味とは
『いりどり』とは、色々なものが混ざり合っている状態を指します。何かを選び抜くことなく、多様な要素や要素が組み合わさった状態です。
類語・言い換えや詳細
1. 多種多様なものが混ざり合っている状態
2. 色とりどりのさま
『筑前煮』の意味とは
『筑前煮』は、兵庫県や福岡県などの一部地域で作られる郷土料理の一つです。具材としてごぼうや人参、こんにゃく、鶏肉などを煮込んだ料理で、甘辛い味付けが特徴です。
類語・言い換えや詳細
1. 兵庫県や福岡県などの一部地域で作られる郷土料理
2. ごぼうや人参、こんにゃく、鶏肉などの具材で作られる
3. 甘辛い味付けが特徴の料理
『いりどり』と『筑前煮』の違いと使い方
『いりどり』と『筑前煮』の違いは、意味と使い方にあります。
『いりどり』はさまざまなものが混ざり合っている状態を表し、色とりどりのさまを示します。具体的な料理として使用されることはありません。
一方、『筑前煮』は特定の料理を指し、兵庫県や福岡県などの地域で食べられる郷土料理です。具材や味付けが特徴であり、料理の名称として使われます。
したがって、『いりどり』は多様なものが混ざり合っている状況全般を指し、『筑前煮』は特定の料理を指す言葉として使用されることになります。
まとめ
『いりどり』は多様なものが混ざり合っている状態を指す言葉であり、『筑前煮』は兵庫県や福岡県などで作られる郷土料理を指す言葉です。意味と使い方に違いがありますので、注意して使い分けましょう。