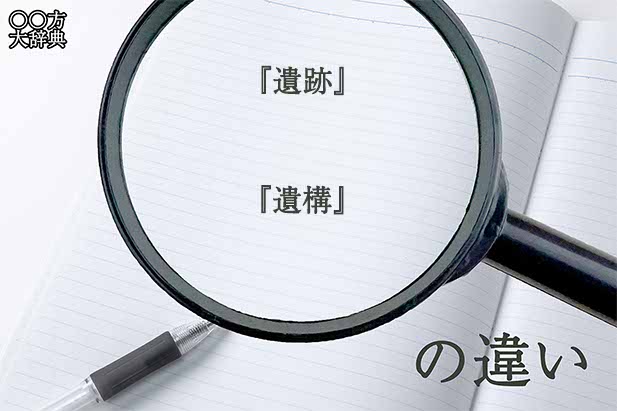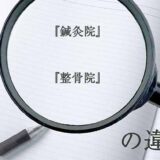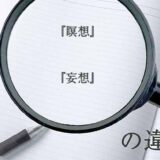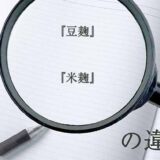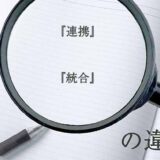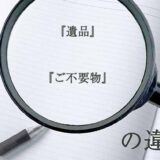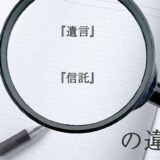この記事では『遺跡』と『遺構』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『遺跡』の意味とは
遺跡(いせき)とは、古代の文化や歴史の証跡となる場所や遺物のことを指します。遺跡は歴史的な価値や文化的な意義があり、研究や保存の対象となります。
類語・言い換えや詳細
1. 文化財
2. 文化遺産
3. 古代遺跡
4. 墓地
5. 遺物
『遺構』の意味とは
遺構(いこう)とは、過去の建物や構造物の一部が現在に残っている跡のことを指します。遺構は建築物や土木構造物だけでなく、古代の遺跡や古墳などの一部も含まれます。遺構は歴史的な遺産や建築の研究に重要な情報を提供します。
類語・言い換えや詳細
1. 建造物の一部
2. 残骸
3. 遺跡の一部
4. 古代建築物
5. 文化的な残り物
『遺跡』と『遺構』の違いと使い方
『遺跡』と『遺構』の違いは、遺跡が古代の文化や歴史の証跡となる場所や遺物を指すのに対し、遺構は過去の建物や構造物の一部が現在に残っている跡を指します。遺跡は通常、広い範囲を含む場所や集合体として扱われ、遺構は一部の残り物として扱われます。具体的な使い方は、遺跡の発掘や保存、研究において「遺跡の発見」「遺跡の調査」「遺跡の保存」などの表現が使われます。一方、遺構は「建物の遺構」「古代建築物の遺構」「遺構の保存」といった表現が使われます。
まとめ
遺跡と遺構は、古代の文化や歴史を理解するために重要な情報を提供します。遺跡は広い範囲を含み、古代の遺物や文化財が存在します。一方、遺構は建物や構造物の一部の残り物であり、建築や文化の研究に役立ちます。遺跡と遺構は使い方や文脈によって使い分けることが重要です。