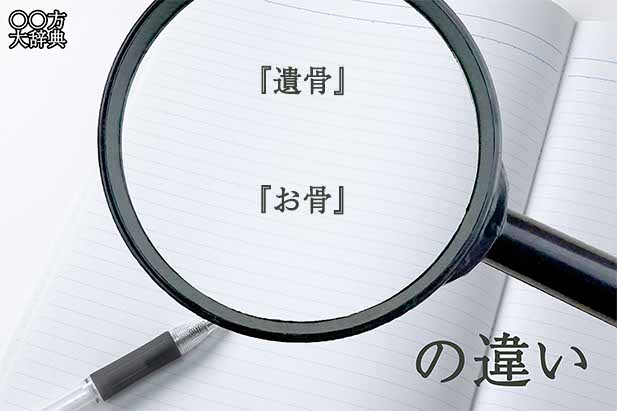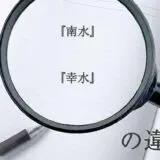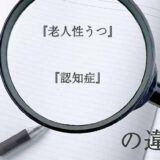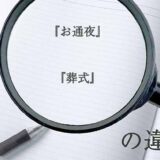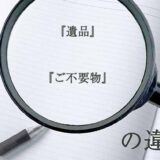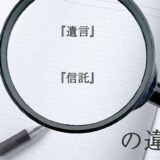この記事では『遺骨』と『お骨』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『遺骨』の意味とは
「遺骨」とは、亡くなった人や動物の死後、火葬を行った際に残る骨のことを指します。具体的には、骨壺や遺骨箱に納められることが多いです。遺骨は故人や愛しいペットとの絆を感じ、供養や思い出として大切にされます。
類語・言い換えや詳細
1. 遺骨は亡くなった人や動物の火葬後に残る骨のことです。
2. 骨壺や遺骨箱に納められることが一般的です。
3. 遺骨は供養や思い出として大切にされます。
『お骨』の意味とは
「お骨」とは、お茶碗の底についているご飯のことを指します。ごはんを食べる際に、お茶碗の底にはお骨ができることがあります。特に子供たちは、お骨を残してしまうことが多いですが、食べ残すことは良くありません。食べ終わったら、お骨をきれいにしましょう。
類語・言い換えや詳細
1. 「お骨」とは、お茶碗の底についているご飯のことです。
2. お茶碗の底にお骨ができることがあります。
3. 食べ終わったら、お骨をきれいにしましょう。
『遺骨』と『お骨』の違いと使い方
「遺骨」と「お骨」は、意味も使い方も異なります。『遺骨』は亡くなった人や動物の火葬後に残る骨を指し、故人や愛しいペットとの思い出として大切にされます。一方で、『お骨』はお茶碗の底についているご飯のことであり、食事の際にきちんと食べるべきです。間違って使ってしまうと誤解を生むことがあるので、注意が必要です。
まとめ
– 「遺骨」とは亡くなった人や動物の死後に残る骨を指し、供養や思い出として大切にされます。
– 「お骨」とはお茶碗の底についているご飯のことで、きちんと食べるべきです。
– 「遺骨」と「お骨」は意味も使い方も異なるので、注意して使い分けましょう。