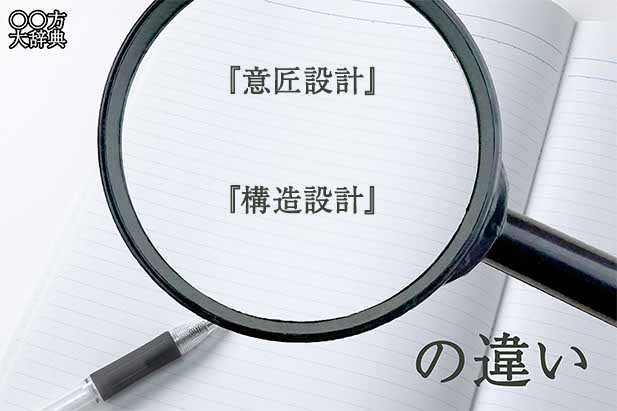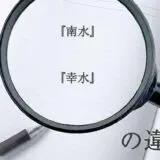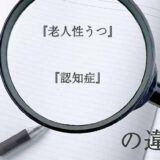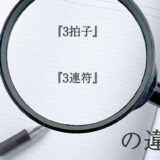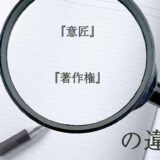この記事では『意匠設計』と『構造設計』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『意匠設計』の意味とは
『意匠設計』とは、建物や製品などの外観や形状をデザインすることです。具体的には、美しさや使い勝手、機能性などを考慮してデザインを行います。例えば、建物の外観やインテリアの配置、製品のデザインなどが『意匠設計』の範疇に含まれます。また、デザインの要素だけでなく、文化や環境に合わせた配慮も重要です。
類語・言い換えや詳細
1. デザイン
2. 美しさ
3. 形状
4. 外観
5. 使い勝手
6. 機能性
7. 建物の外観
8. インテリアの配置
9. 製品のデザイン
10. 文化や環境に合わせた配慮
『構造設計』の意味とは
『構造設計』は、建物や製品の耐力や安定性を考慮して設計することです。具体的には、建物の柱や梁の配置、製品の材料や組み立て方法などを計画し、安全かつ効率的な構造を構築します。『構造設計』は、建物や製品が正しく機能し、長持ちするために欠かせない要素です。
類語・言い換えや詳細
1. 耐力
2. 安定性
3. 建物の柱や梁の配置
4. 製品の材料
5. 組み立て方法
6. 安全性
7. 効率性
8. 正しい機能
9. 耐久性
『意匠設計』と『構造設計』の違いと使い方
『意匠設計』と『構造設計』の違いは、デザインと構造にあります。『意匠設計』は、外観や形状、デザインの面を重視して設計するのに対し、『構造設計』は、耐力や安定性、機能性などの面を重視して設計します。使い方としては、建物を設計する際には、まず『意匠設計』で外観や配置を決め、次に『構造設計』で安全性や耐久性を確保します。
まとめ
『意匠設計』と『構造設計』は、建物や製品を設計する際に重要な要素です。『意匠設計』は美しさや使い勝手、機能性を追求し、『構造設計』は耐力や安定性を確保するために行われます。両者を適切に組み合わせることで、優れたデザインと構造を実現することができます。