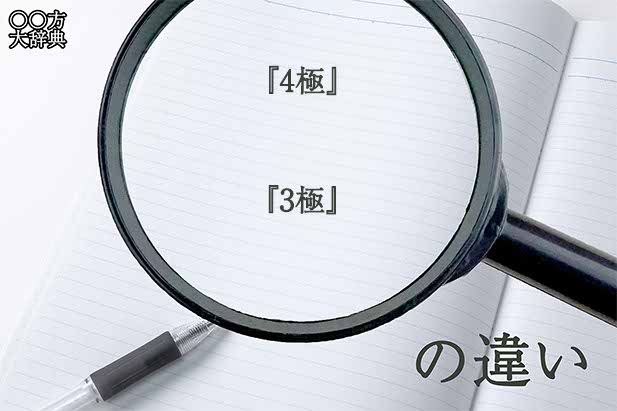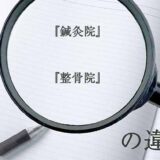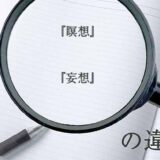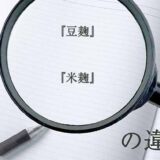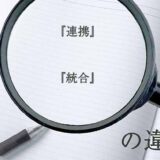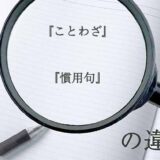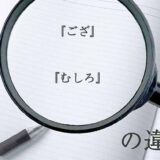この記事では『4極』と『3極』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。
それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『4極』の意味とは
『4極』とは、物事や意見が4つの異なる要素や要点に分かれていることを指します。それぞれの要素は、それぞれ異なる状態や特徴を持っており、全体を成す要素としての役割を果たします。例えば、4極からなる意見がある場合、それぞれの極には異なる意見や立場があり、全体の議論や結論を形成する際に重要な役割を果たします。
類語・言い換えや詳細
1. 要素の状態や特徴が異なる。
2. 4つの要素が全体を成す。
3. 意見や立場の異なる極がある。
4. 議論や結論に重要な役割を果たす。
『3極』の意味とは
『3極』とは、物事や意見が3つの異なる要素や要点に分かれていることを指します。これは『4極』と同様に、それぞれの要素が異なる状態や特徴を持っており、全体を成す要素としての役割を果たしますが、要素の数が4つではなく3つである点が異なります。例えば、3極からなる意見がある場合、それぞれの極には異なる意見や立場があり、全体の議論や結論を形成する際に重要な役割を果たします。
類語・言い換えや詳細
1. 要素の状態や特徴が異なる。
2. 3つの要素が全体を成す。
3. 意見や立場の異なる極がある。
4. 議論や結論に重要な役割を果たす。
『4極』と『3極』の違いと使い方
『4極』と『3極』の違いは、要素の数にあります。『4極』は4つの要素で構成されており、『3極』は3つの要素で構成されています。また、それぞれの要素が異なる状態や特徴を持っており、全体を成す要素としての役割を果たします。使い方では、具体的な物事や意見において異なる要素や要点が4つある場合は『4極』を、3つある場合は『3極』を用いることが適切です。
まとめ
『4極』と『3極』は、物事や意見の要素や要点の数を表す言葉です。『4極』は4つの要素で構成されており、『3極』は3つの要素で構成されています。それぞれの要素は異なる状態や特徴を持ち、全体を形成する際に重要な役割を果たします。使い方では、要素や要点の数に合わせて正確に使用しましょう。