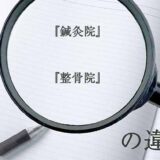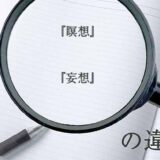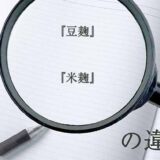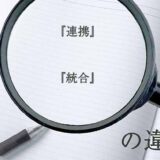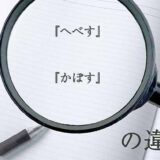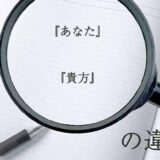この記事では『ぶり』と『はまち』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『ぶり』の意味とは
『ぶり』は、魚の一種であり、「ブリ」とも呼ばれています。主に日本料理で使われることが多く、その特徴は、肉質がやわらかく、脂が乗っていて風味があります。刺身や焼き物、煮物など、さまざまな調理法で食べられます。
類語・言い換えや詳細
1. 魚の一種である。
2. 刺身や焼き物、煮物など、さまざまな調理法で食べられる。
3. 肉質がやわらかく、脂が乗っている。
4. 日本料理でよく使われる。
『はまち』の意味とは
『はまち』もまた、魚の一種であり、「ハマチ」とも呼ばれています。ぶりと同様に日本料理でよく使われますが、ぶりよりもさっぱりとした味わいが特徴です。主に刺身や寿司のネタ、また焼き魚として食べられます。
類語・言い換えや詳細
1. 魚の一種である。
2. 刺身や寿司のネタ、焼き魚として食べられる。
3. ぶりよりもさっぱりとした味わいがある。
4. 日本料理でよく使われる。
『ぶり』と『はまち』の違いと使い方
『ぶり』と『はまち』の違いは、主に味わいにあります。ぶりは脂が乗っていて風味があり、肉質がやわらかいため、がっしりとした味わいを楽しむことができます。一方、はまちはさっぱりとした味わいが特徴で、ぶりよりも軽やかな食べごたえがあります。使い方としては、ぶりは刺身や焼き物、煮物などさまざまな料理に使われ、特に日本料理でよく見られます。一方、はまちは主に刺身や寿司のネタ、焼き魚として使用されます。
類語・言い換えや詳細
1. 味わいの違い: ぶりはがっしりとした味わい、はまちはさっぱりとした味わい。
2. 使用法の違い: ぶりは刺身や焼き物、煮物などさまざまな料理に使われる。はまちは主に刺身や寿司のネタ、焼き魚として使用される。
3. ぶりの特徴: 脂が乗っていて風味があり、肉質がやわらかい。
4. はまちの特徴: ぶりに比べてさっぱりとした味わいがある。
まとめ
『ぶり』と『はまち』は、どちらも美味しい日本料理の素材ですが、使用法や味わいに違いがあります。ぶりはがっしりとした味わいを楽しむことができる一方、はまちはさっぱりとした食べごたえがあります。自分の好みや料理のテーマに応じて適切に選びましょう。