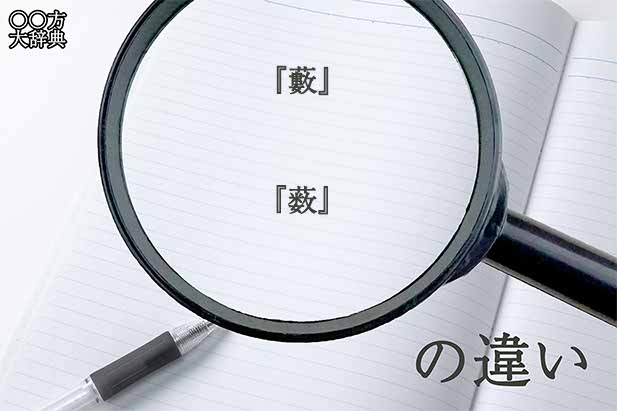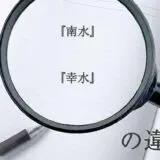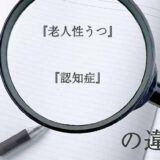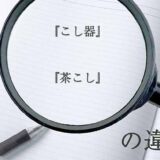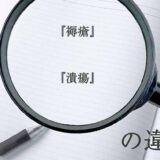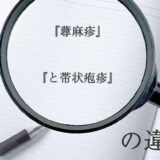この記事では『藪』と『薮』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『藪』の意味とは
『藪』は、日本語において自然界に存在する植物や木々が集まってできた茂みのことを指します。主に山や森林に見られることが多く、しばしば迷いやすい地形としても知られています。また、日本の伝統的な文化や文学においても『藪』は重要な要素として取り上げられることがあります。
類語・言い換えや詳細
1. 茂み
2. 林
3. 樹木の集まり
『薮』の意味とは
『薮』も『藪』と同じく自然界の植物の集まりを指しますが、より草や低木に特化しています。『薮』は主に湿地や川の近く、土地の低い場所に見られることが多く、茂った草や低い木々が繁茂している様子を表現する際に使われます。また、『薮』は時に複雑で迷路のような場所や事物を意味することもあります。
類語・言い換えや詳細
1. 草むら
2. 低木の集まり
3. 迷路のような場所
『藪』と『薮』の違いと使い方
『藪』と『薮』の最も大きな違いは、「植物の種類と茂り方」です。『藪』は木々が集まってできる茂みを指し、自然界の植物の多様な種類が含まれます。一方、『薮』は主に草や低木が繁茂している様子を表現し、茂り方がより密集している傾向があります。また、『藪』は伝統的な文学や文化においても重要な意味を持ち、雅や風流なイメージがあります。一方、『薮』はより野生的で荒々しさを感じさせます。
使い方では、『藪』は山や森林などの自然環境を指す場合や、文章や歌において比喩的に使われることが多いです。一方、『薮』は湿地や川の近く、平地の低い場所など、具体的な場所を表現する際に使われることが一般的です。また、迷路のような場所を表現する場合にも『薮』がよく使われます。
まとめ
『藪』と『薮』は、自然界の植物の集まりを指す言葉ですが、種類や茂り方に違いがあります。『藪』は木々が集まった茂みであり、伝統的な文化や文学において重要な意味を持ちます。『薮』は草や低木が繁茂し、湿地や川の近くなどで見られることが多いです。使い方では、『藪』は自然環境を指す場合や比喩的な表現に使われ、『薮』は具体的な場所や迷路のような場所を表現する際に使われます。