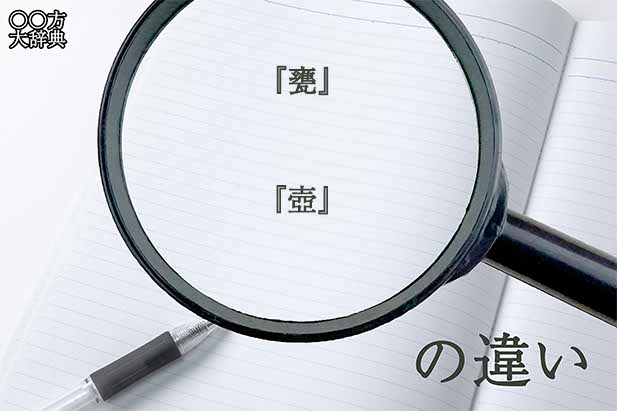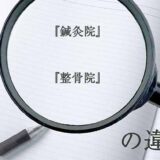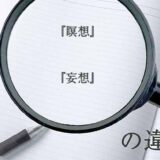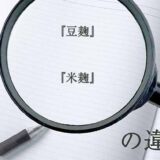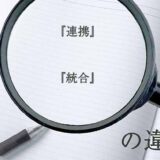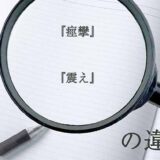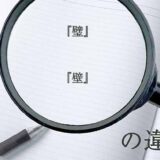この記事では『甕』と『壺』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『甕』の意味とは
甕(かめ)とは、容器の一種であり、主に土や陶器で作られるものを指します。中には水や酒、調味料などを入れることができます。古くから使われており、主に食品の保存や調理に使われることが多いです。
類語・言い換えや詳細
1. 土や陶器で作られる容器
2. 主に食品の保存や調理に使われる
『壺』の意味とは
壺(つぼ)とは、容器の一種であり、主に陶器や金属で作られるものを指します。甕と同様に液体や調味料を入れることができますが、壺は主に花や酒を入れるために使用されます。容器の形状や使用目的が甕とは異なるため、使い分けが必要です。
類語・言い換えや詳細
1. 陶器や金属で作られる容器
2. 主に花や酒を入れるために使われる
『甕』と『壺』の違いと使い方
甕と壺の違いは、材質や使用目的にあります。甕は食品の保存や調理に使われる一方、壺は花や酒を入れるために使用されます。また、甕は主に土や陶器で作られ、壺は陶器や金属で作られることが一般的です。使い方を間違えてしまうと、容器が破損したり、中身がこぼれたりする可能性がありますので、注意が必要です。
まとめ
甕と壺は容器の一種であり、どちらも液体や調味料を入れることができます。ただし、甕は土や陶器で作られ、食品の保存や調理に使われるのに対し、壺は陶器や金属で作られ、花や酒を入れるために使用されます。使い方を間違えないようにしましょう。