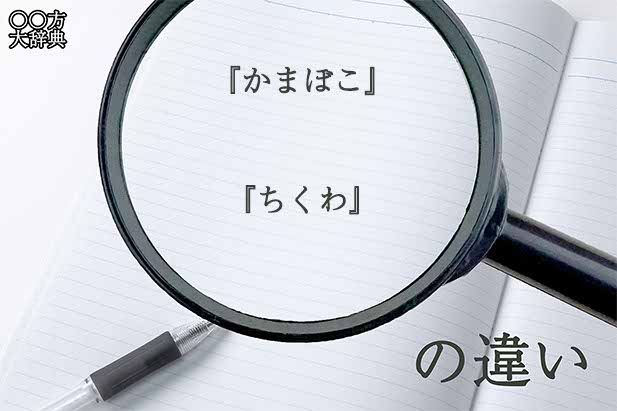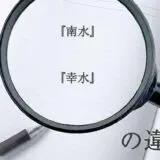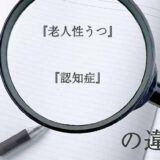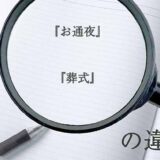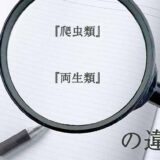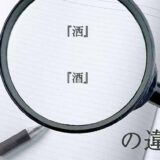この記事では『かまぼこ』と『ちくわ』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『かまぼこ』の意味とは
かまぼこは、魚のすり身やタンパク質を使用して作られる日本の伝統的な食べ物です。主に練り製品として販売されており、魚のすり身を成形して蒸し焼きにしたものです。見た目は楕円形で、一般的なかまぼこの色は淡いピンク色です。一般的な使い方は、おでんや各種汁物、独特の風味を楽しむためにそのまま食べることもあります。
類語・言い換えや詳細
1. すり身 – 魚の身をすりおろしたもの
2. タンパク質 – 筋肉や皮膚の主成分で、栄養摂取に重要な役割を果たす
『ちくわ』の意味とは
ちくわは、魚のすり身を成形して繊維の方向として竹輪を作る日本の伝統的な食べ物です。一般的なちくわは白色で、円筒形をしています。主に焼いて食べることが一般的で、おでんや串焼きなどで使われます。また、そのまま食べることもあります。
類語・言い換えや詳細
1. 繊維 – 食材や布地などの細長い部分
2. 串焼き – 食材を串に刺して焼く料理の一つ
『かまぼこ』と『ちくわ』の違いと使い方
かまぼことちくわは両方とも魚のすり身を使って作られていますが、形や食べ方に違いがあります。かまぼこは楕円形で、蒸し焼きになるのに対して、ちくわは円筒形で焼き上げられます。また、かまぼこの一般的な使い方はおでんや汁物に入れて食べることが多く、ちくわは焼いて食べることが一般的です。
まとめ
『かまぼこ』と『ちくわ』は、どちらも魚のすり身を使った日本の伝統的な食べ物ですが、形や使い方に違いがあります。かまぼこは蒸し焼きにしておでんや汁物に入れて食べることが一般的で、ちくわは焼いてそのまま食べることが一般的です。しっかりと違いを理解し、食事の際に適切に使い分けましょう。