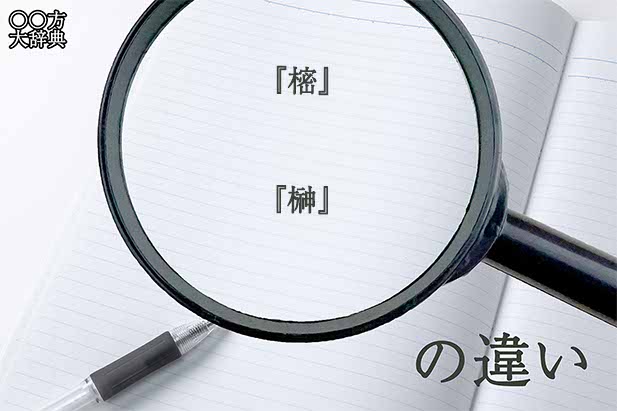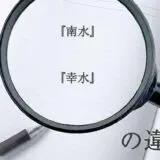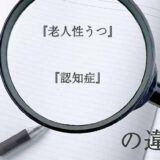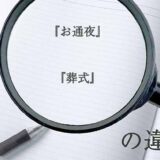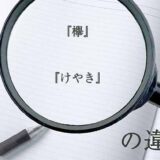この記事では『樒』と『榊』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『樒』の意味とは
『樒』(ふし)は、木の名前です。主に暖地で育ち、高さ約10mほどに成長することが多い樹木です。葉は広がり、美しい形状をしています。また、樹皮には特有の香りがあり、香木としても利用されます。
類語・言い換えや詳細
1. 樹木の名前
2. 暖地で育つ
3. 高さ約10mほど
4. 葉の形状が美しい
5. 樹皮に特有の香り
『榊』の意味とは
『榊』(さかき)は、日本の伝統的な木の名前です。主に神道の祭壇やお守りなどに使われることが多いです。葉は小さく、光沢があり、特に新緑の季節に美しく輝きます。また、榊は神聖な木とされており、特別な場で用いられることが多いです。
類語・言い換えや詳細
1. 日本の伝統的な木
2. 神道の祭壇やお守りに使用
3. 小さな葉で光沢があり美しい
4. 神聖な木
5. 特別な場で用いられる
『樒』と『榊』の違いと使い方
『樒』と『榊』の主な違いは、まず起源です。『樒』は普通の木の名前であり、特別な意味合いはありません。一方で、『榊』は神聖な木とされ、神道の儀式や場で用いられることが多いです。また、使い方でも異なることがあります。『樒』は主に木材や香木として利用されることが多く、香りを楽しむことが目的です。一方で、『榊』は神道の祭壇やお守りなどに使用され、神秘的な力を持つと信じられています。
類語・言い換えや詳細
1. 起源が異なる
2. 『樒』は普通の木として利用される
3. 『榊』は神聖な木として利用される
4. 『樒』は主に木材や香木として使われる
5. 『榊』は神道の祭壇やお守りに使用され、神秘的な力を持つ
まとめ
『樒』と『榊』は、どちらも木の名前ですが、意味や使い方には違いがあります。『樒』は主に木材や香木として利用され、その特有の香りを楽しむことができます。一方で、『榊』は神聖な木であり、神道の祭壇やお守りなどに使用されます。それぞれの特徴を理解し、適切な場面で使い分けましょう。