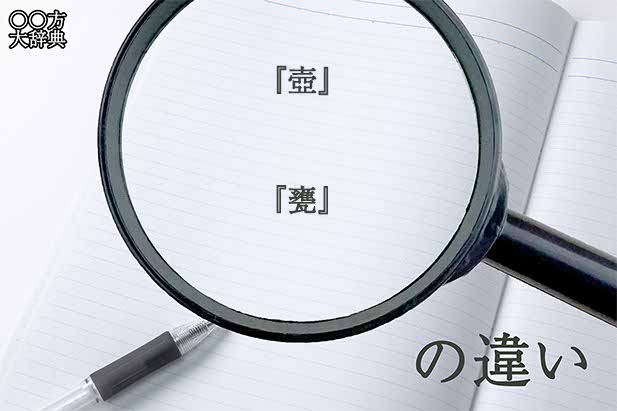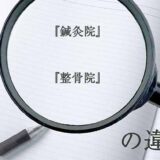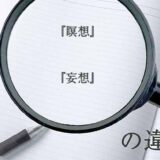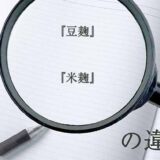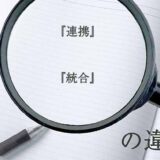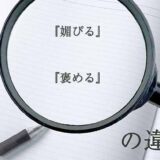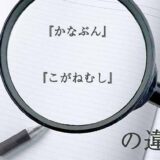この記事では『壺』と『甕』の違いについてをわかりやすく講義させて頂きます。それぞれの意味と使い方や表現を理解してしっかり使い分けましょう。
『壺』の意味とは
『壺』(つぼ)とは、土や陶器、ガラスなどで作られた容器の一つです。古くから水や酒、調味料などを入れるのに使われてきました。大きさや形状は様々であり、装飾品や美術品としても使われることがあります。
類語・言い換えや詳細
1. 土や陶器、ガラスなどで作られる
2. 水や酒、調味料などを入れるのに使われる
3. 大きさや形状は様々
『甕』の意味とは
『甕』(かめ)とは、大きな土製の容器の一種です。主に醸造や保存などに使用されます。古来より穀物やお酒の保存に用いられてきました。特に日本では、古代から現在まで伝統的な酒造りに欠かせない存在です。
類語・言い換えや詳細
1. 大きな土製の容器
2. 醸造や保存に使用される
3. 穀物やお酒の保存に用いられる
『壺』と『甕』の違いと使い方
『壺』と『甕』の違いは、素材や用途にあります。『壺』は土や陶器、ガラスなどで作られ、水や酒、調味料などを入れるために使用されます。一方、『甕』は主に大きな土製の容器であり、醸造や保存に使用されます。例えば、酒造りや食品の保存には『甕』が使われることが一般的です。
類語・言い換えや詳細
1. 壺:水や酒、調味料などを入れる
甕:醸造や保存
2. 壺:土や陶器、ガラスなど
甕:大きな土製の容器
3. 壺:装飾品や美術品としても使われることがある
甕:日本の伝統的な酒造りに欠かせない
まとめ
『壺』と『甕』は、素材や用途が異なるため、使い分けが重要です。『壺』は水や酒、調味料の入れ物として、また装飾品や美術品として使われます。一方、『甕』は醸造や保存に使用され、特に日本の酒造りに欠かせない存在です。正しい使い方を覚え、適切に利用しましょう。